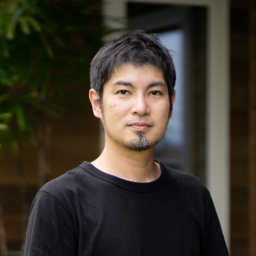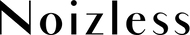玄関周りに統一感を生み出す、ミニマルなエントランスユニット(中編)
森田アルミ工業株式会社の内藤正宏さんへのインタビュー。中編ではポストとインターホンパネルのデザインについて伺います。

投函口を見せない、2段階構造の扉。
―ドアの開き方や、ポストとインターホンパネルの配置。一見何気ないことに見えますが、すべて合理的な理由があるんですね。
〈内藤〉そこまでが最初に決まり、次に、建築になじませるためにどうシンプルにつくるかを検討しました。
主張させたくないので、ポストの投函口を見えないようにしたい。また、前面に突き出すような取っ手も使いたくない。
それで、四角の中に扉を設け、手前に引いたら上に投函口が出てきて、投函口のロックを解除したらさらに開いて物を取り出せるという2段階構造にすれば、その条件をすべてクリアできるだろうと考えました。
清掃ができるように、さらに90度まで開くことができるのですが、この計3段階で開く技術は今特許を出願しているところです。

―ポストのドアの取っ手もとてもシンプルに目立たないようにデザインされていますね。
〈内藤〉J取っ手に手を掛けて開く仕組みなので、「そこに取っ手がある」というよりは、ちょっとしたスリットに手を掛けられるという感じですね。
ポスト・インターホン・表札が一体になるというコンセプトなんですけど、ポスト単体でもきれいに見せて単体でもしっかり量を売ることができれば、コストを抑えやすくなると考えました。

例えばリフォームの場合ですと、既に設置されているインターホンを一度外すのは手間なので、ポスト単体の方が購入しやすいと考えられます。
過酷な試験を経て、確かな耐久性も実現。
―次に開発で苦労したことや難しかったことを教えて頂けますか?
〈内藤〉苦労したことは大きく2点あり、その1つはポストの強度ですね。
ポストをシンプルにつくるためには、薄いフレームに取っ手があって、扉ごと開く構造にする必要があるのですが、最初の試作品ではゴムの弾性で開いた扉を固定する構造にしていました。
ちなみに製品化をするには強度試験をクリアする必要があります。ポストの上に31kgの重りを載せたり、水平方向に150N(ニュートン)の力で押し続けたり、ポストの中に16kgの板を入れたり…とかですね。
一番過酷な試験は、開いた状態の扉に100N(11kg)の荷重を掛けて24時間放置するというものでした。これが最初のゴムを使った構造では試験前から無理だと想像できたので、フラットバーで荷重を支える機構にやり替えてクリアしました。

それから扉の開閉を15,000回繰り返したり、300Nの力で引っ張ったり、毎分6リットルの水を15分散水して内部に水が侵入しないことを確認したりといった試験も行いました。
ホームセンターに行けば安価なポストも販売されていますが、僕たちは建築と一緒になるものと捉え、しっかり強度を持たせたいと思っていました。それで厳しい基準を自分たちで設定し、改良を繰り返していました。そこが苦労したところです。
箱のデザインから、フレームのデザインへ。
―デザインがシンプルで美しいだけでなく、しっかりとした強度と耐久性も備わっているんですね。苦労したこと2点目はどんなことですか?
〈内藤〉2点目はインターホンパネルのデザインです。ポストはデザインを決定するための条件が多かったので収束させやすかったですが、インターホンパネルに関してはインターホンが付けられればいいので最初はただの四角いボックスにしたんです。
しかし、ボックス型のパネルの試作ができ上がって見ると、ポストとの一体感が足りませんでした。
インターホンパネルは箱のデザインですが、ポストはフレームのデザインになっています。色・素材・サイズはそろっていますが、デザインの言語がそろっていない感じがしたんですね。
 試作時のインターホンパネルとポスト。
試作時のインターホンパネルとポスト。
そこで箱型をやめて、ポストに合わせる形でフレームを作って、前に板を付ける構造に変更しました。そして、その板を付けるのにビスを使うと正面にビスが見えてしまうので、板バネを使ってバチンとはめ込む構造にしました。
板を外してみると、それぞれのパーツに突起が付いていて、それが合わさってバチンとはまる仕組みです。
 インターホンパネルの取り付け用突起パーツ
インターホンパネルの取り付け用突起パーツ
この仕組みにしたことで、前の板以外を組み立てた状態で正面からビスを打てる構造にできました。実は最初の試作段階ではインターホンパネルの下にビスを打つ場所があり、インターホンパネル設置後にポストを取り付ける仕組みになっていました。
そうすると、ポストを付けた後にインターホンが壊れてしまったら、インターホンを外すためにポストも外さなければならなかったんです。板バネで取り付ける仕様にしたことで、その問題も併せて解決できました。
その後さらにビスを打つ場所を見直し、インターホンが関係しない場所で4点留めできるようにして、さらに簡単に施工ができるようになりました。
 インターホンパネルを固定する4つのビスは、全てインターホンの右側にある。
インターホンパネルを固定する4つのビスは、全てインターホンの右側にある。
あと、試作段階では箱型にするためにサイズが大きくなっていたんですが、正面の幕板をはめる構造にしたことで高さが抑えられ、横方向に細長いデザインにできました。
―箱型かフレーム型か。本当にわずかな違いですが、比べてみるとずいぶんと印象が変わりますね。ちなみにどんなインターホンにも対応できるんですか?
〈内藤〉日本のインターホン市場はPanasonicさんとアイホンさんの2社がほぼ独占していて、上下左右のサイズが規格化されているんです。
奥行だけは規格化されていないので、異なる奥行に対応できるように取り付け位置は前後の調整ができる機構にしています。

ただ、各社のハイグレードモデルだけは上下左右のサイズが大きいため取り付けができません。インターホンパネルのサイズをコンパクトにしたかったので、ハイグレードモデルにはあえて対応しない仕様にしました。
– 中編はここまでです。次回の後編では、表札のこだわりについてご紹介します。
後編はこちらから→
〈関連ページ〉
内藤正宏 一級建築士
ないとうまさひろ・1989年生まれ。山梨県甲府市の材木屋に生まれる。2014年 芝浦工業大学大学院理工学研究科建設工学専攻卒。同年 大手住宅系組織設計事務所勤務、2019年 森田アルミ工業株式会社勤務を経て、2021年株式会社レクトを設立。