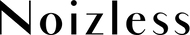【パーツ探訪】丸山 弾さんに訊く「風景と響き合う空間設計の作法」前編
街中の家でも、郊外の家でも、森の中の家--どんな土地でも気持ちが良いのは、建築と周辺の環境が滑らかに繋がっていくから。
「高気密高断熱の時代になり、建築が内向きになっていくなか、やはり外とのつながりは大切にしていきたい」と語る建築家の丸山弾さん。
家族の成長とともに住まい手の生活が変化しても空間の秩序が乱れないのは、見えないところまで計算し尽くされた設計の賜物。それでいて身構えたような堅苦しさはなく、おおらかな空気が流れています。
人と空間、住まいと土地との関係をていねいに紡いでいき、その場所でしか生まれない住空間をつくり続けてきた丸山さん。その設計手法を、ディテールや建材を通じて探ります。
 [プロフィール]丸山弾:1975年東京都生まれ。1998年成蹊大学卒業。2003年堀部安嗣建築設計事務所入所。2007年丸山弾建築設計事務所設立2022年丸山弾-スタジオに改称。2007〜2024年京都芸術大学大学院非常勤講師、2024年より日本大学芸術学部非常勤講師。
[プロフィール]丸山弾:1975年東京都生まれ。1998年成蹊大学卒業。2003年堀部安嗣建築設計事務所入所。2007年丸山弾建築設計事務所設立2022年丸山弾-スタジオに改称。2007〜2024年京都芸術大学大学院非常勤講師、2024年より日本大学芸術学部非常勤講師。

今回訪れた「つくばの家」は、広く開けた小麦畑を前にした敷地に立つ住まい。のどかな風景に呼応するように、伸びやかな切妻屋根を架け、外壁は杉板でまとめています。
建物は前面道路から奥へと控え、庭をたっぷり確保。外との距離をとりながらも、自然を身近に感じられるよう計画されました。
庭に面した1階には、薪ストーブを備えた吹抜けのLDKを配置。恵まれた外部環境を活かして、明るさと開放感を軸にしつつも、あえて陰やズレを織り交ぜて、空間に奥行きと落ち着きをもたらしています。

玄関は奥に引き込み、光を抑えた廊下を抜けると、開放的なLDKへと導かれる構成。共働き世帯のために、玄関まわりに洗面・トイレ・脱衣所・浴室をまとめ、効率的な家事動線を確保しています。2階は寝室などの個室をまとめ、階を隔てながらも家族の気配が自然につながるよう計画されています。
#1 空間の中にシームレスに存在するキッチン
 アイランド型カウンターと壁付けカウンターを組み合わせた、広々としたキッチン。キッチンそのものは特別なことはやっていないのですが……と話す丸山さんですが、驚くほどの一体感で、空間にぴたりと馴染んでいます。
アイランド型カウンターと壁付けカウンターを組み合わせた、広々としたキッチン。キッチンそのものは特別なことはやっていないのですが……と話す丸山さんですが、驚くほどの一体感で、空間にぴたりと馴染んでいます。
それは、建築とキッチンの逃げをつくらないつくり方をしているため。
建築と造作(家具・建具など)では求められる精度が違い、たとえば建築ではミリ単位での誤差が許容されるのに対し、造作はミリ以下と異なります。なので、建築にぴったり合わせてつくる造作は、異なる精度同士のものを取り合わせるということに。そして一般的には施工誤差を吸収するため、建築と造作の取り合いには、「逃げ」をつくります。
この「逃げ」を、丸山さんはつくりません。言うは易し……ですが、設計上のテクニックはもとより施工側との阿吽の呼吸も必要になります。
 丸山さんの造作を長年にわたり支えているのが、オーダーメイドのキッチン・洗面台・家具ブランドRILNOを手掛ける田中工藝。「よい意味での緊張感をキープしたい」という考えから、取り合いの精度にはこだわる。
丸山さんの造作を長年にわたり支えているのが、オーダーメイドのキッチン・洗面台・家具ブランドRILNOを手掛ける田中工藝。「よい意味での緊張感をキープしたい」という考えから、取り合いの精度にはこだわる。
丸山さんが心がけているのは、通常は別々に描く枠周りや家具の詳細図を、同時に描くということ。枠周りは建築、家具は造作といった異なる精度をもつものを一体として詰めていくことができる、というのがその理由です。
また「現場変更はしない」というのも、長年にわたり大切にしているポリシーだそう。
「現場で考えると部分的にしか見えなくなって、全体との関係が崩れてしまいます。現場変更をすると、施工側が混乱するし、デメリットが多い、というのが持論です。事前に図面の中で全体を見ながら部分を決めるほうが、空間のバランスが整います」と丸山さんは語ります。
 LDKから北側を見る。廊下の左側に階段、洗面・トイレ、右側に玄関、脱衣所・浴室がある。住まいの中には明るい場所もあれば、暗い場所もあるのが気持ちが良い、と語る丸山さん。北側は光を抑えているが、暗くなりすぎないように小窓で採光を得る。
LDKから北側を見る。廊下の左側に階段、洗面・トイレ、右側に玄関、脱衣所・浴室がある。住まいの中には明るい場所もあれば、暗い場所もあるのが気持ちが良い、と語る丸山さん。北側は光を抑えているが、暗くなりすぎないように小窓で採光を得る。
 キッチンの壁と天井の取り合い。微妙なズレをつくって空間が「ぬるぬる」つながっていくような印象を演出している。
キッチンの壁と天井の取り合い。微妙なズレをつくって空間が「ぬるぬる」つながっていくような印象を演出している。
#2 空間に整然となじむ一体型のラバトリーボウル
 最近はベッセル型の洗面ボウルも人気を博していますが、丸山さんの定番は、ラバトリーボウルと天板が一体になったタイプ。
最近はベッセル型の洗面ボウルも人気を博していますが、丸山さんの定番は、ラバトリーボウルと天板が一体になったタイプ。
「やっぱり水が飛び散ってしまうので、掃除がラクなデザインをおすすめしています。あと、一体型のメリットは、つなぎ目がないこと。シーリングが汚れるストレスがありません。昔と違って今は共働きのご家庭が増えています。夫婦がいる世帯における共働き世帯の割合は、いまや70%を超えています。
どうしても家事に割ける時間が短くなるので、できるだけ建築側でサポートできればと思います。
このコーリアンのカウンターとボウルはシームレス加工の一体成形で、継ぎ目(シーリング部分)に汚れもたまらず衛生的。もちろん美しく見えるというのもポイントです」
 この天板も壁との逃げを設けず、精緻に施工している。
この天板も壁との逃げを設けず、精緻に施工している。
#3 “使用中”をさりげなく告げるすりガラスの引き戸

トイレや脱衣所の鍵は、丸型の表示錠を使っていますが、「錠は操作するときにわざわざ手を上げないで済むように腰のあたりにつけますが、表示が見えにくいのですよね」と丸山さん。
木製の手掛けの横を掘り込んですりガラスを嵌め込むことで、内部で電気を点けていれば、光がこぼれ、使用中かどうか教えてくれます。
すりガラスなので、人がいることはわかっても内部の様子は見えず、プライバシーの面でも◎。ささやかな光の筋は空間デザインの邪魔にもならず、堅実に仕事をこなしてくれます。

#4 水にも強いスリムな真鍮の取手

取手は掘り込みにする場合もあるけれども、水を使う場所では汚れづらさを考えて、金物をシンプルに付けることも多いそう。
愛用しているのが、堀商店の「430-B」という真鍮の取手です。
洗面所の収納では縦使い、キッチンでは横使い、と、場所や用途に応じて取り付け方を変えています。

「気に入っているのは、太さが7φという細さです。7φ以上は必要以上に存在感が出てしまうので、この太さがギリギリ許容範囲。面材の素材によって、ステンレスか真鍮か使い分けていますが、ステンレスでシャープに見せるのも良いですし、真鍮の経年変化で落ち着いていく感じもいいですね」

#5 面のように見えるグレーの大判タイル
 キッチンをはじめ水回りはモルタル仕上げにするのも悪くないけれども、汚れが染み込んでしまうのがネック。そこで丸山さんが長年にわたり愛用しているのが、「フォンテトレーディング」のタイル(59-59-G400 パールグレー)です。
キッチンをはじめ水回りはモルタル仕上げにするのも悪くないけれども、汚れが染み込んでしまうのがネック。そこで丸山さんが長年にわたり愛用しているのが、「フォンテトレーディング」のタイル(59-59-G400 パールグレー)です。
「昔から使っているのは600㎜角の大判タイル。大判だと目地の本数が少なくて面のように見えますし、方向性を感じさせないのもいい。タイルに微妙に色ムラがあって、フラットな感じにならないのも気に入っています」

#6 山林舎の薪ストーブ
 薪ストーブは設置レイアウトも重要。丸山さんのプラン+断面構成は、上昇した暖気が2階に回りつつ、2階の腰壁が上昇した暖気を程よく受け止め、1階も2階も上手に温めてくれる。
薪ストーブは設置レイアウトも重要。丸山さんのプラン+断面構成は、上昇した暖気が2階に回りつつ、2階の腰壁が上昇した暖気を程よく受け止め、1階も2階も上手に温めてくれる。
リビング・ダイニングの一角には、薪ストーブを。両面がガラスのシースルータイプで、サイズ的にもデザイン的にも圧迫感をもたらしません。コンパクトだけれども、煙突が偏心していることで、薪ストーブのトップにやかんや鍋が置けます。そして、きれいな炎を眺められるすぐれもの。暖炉と異なり薪ストーブは筐体に蓄熱するので、放射熱・輻射熱による体にやさしい暖かさを感じられます。

制作を手がけたのは、長野の「ストーブ工房 山林舎」。丸山さんが独立して初めて手がけた山荘「那須の家(2009年) 」でも、同タイプのストーブをデザインし、制作を山林舎に依頼しています。
山林舎は、建築家がオリジナルデザインで薪ストーブを制作する時に、よく名前が上がるストーブ工房です。山林舎を立ち上げた創設者の故・児玉新時さんは、「薪ストーブは生活用具」というモットーをおもちだった方で、有名な「シェイカーストーブ」も開発。自社のオリジナリストーブをつくりつつ、建築家のオーダーメードを受けており、現在では児玉さんの薫陶を受けた竹内淳さんが二代目として腕をふるっています。

〈このコラムで紹介したパーツ〉
・堀商店 取手「430-B」
・フォンテトレーディング 磁器質タイル「G400」
・ストーブ工房 山林舎

【プロフィール】
丸山 弾 / 丸山弾建築設計事務所
1975年東京都生まれ。1998年成蹊大学卒業。2003年堀部安嗣建築設計事務所入所。2007年丸山弾建築設計事務所設立2022年丸山弾-スタジオに改称。2007〜2024年京都芸術大学大学院非常勤講師、2024年より日本大学芸術学部非常勤講師。
「つくばの家」
茨城県つくば市
敷地面積 366.39㎡
延床面積 121.46㎡
構造規模 木造軸組工法 2階建て
竣工年月 2022年4月
設計 丸山弾(丸山弾-スタジオ)
施工 けんちく工房 邑
造園 舘造園