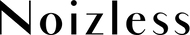【パーツ探訪】 青木律典さんに訊く「住まい手の言葉を膨らませながらつくる ちょうどいい住まいと暮らし」(前編)
奇を衒うことなく、質実に。けれども一度訪れると、深く記憶に刻まれる。やわらかな光と陰影が重なり合う空間は、ずっと身を置いていたいと思わせるほど心地よい。
そんな住まいを数多く手がけるのが、建築家の青木律典さんです。通底するのは、暮らしへの優しい眼差し、手触りのよい素材、精緻な納まり、そして現実的なコスト感覚。
一見当たり前のように思えるけれども、それを徹底的にやり抜くことで、ふくよかな豊かさが宿る空間が生まれます。
住まい手からは「気になるノイズがない」と評されることも。そんな青木さんの設計手法を、パーツやディテールから読み解きます。

[プロフィール]1973年神奈川県横浜市生まれ。2003年日比生寛史建築計画研究所。2005年田井勝馬建築設計工房。2010年青木律典建築設計スタジオ設立。2015年株式会社デザインライフ設計室に改組。
今回訪れた「格子出窓の家」は、築50年ほど前に造成された街区の一角の、住宅の建て替えです。街区は短冊状に分割されており、どの家も南側に庭を、北側に建物が規則正しくレイアウトされています。一方でこの住まいだけ、南と北に分割された南側の土地に建つイレギュラーな状況でした。その特性を活かして、街区南側の緑とつながりをもてるように植栽でうるおいをつくり、2階からは緑の上空に視線が抜けるように計画しています。
住まい手から求められたのは、明るさと開放感、防犯性、そして飛来物などにより割れにくい窓、というもの。この要件を解くために青木さんが考案したのが、窓を大きな出窓にする、ということでした。出窓により、明るくのびやかな空間を叶え、出窓の外側に木製の格子を取り付けることで、防犯性を高め、飛来物への対策ともしている「一石三鳥」の方法論です。

1階はLDKと洗面・浴室、個室、2階は個室とラウンジという構成。

#1空間に合わせた造作家具で、LDKをスッキリと

以前建っていた住まいと比べて、床面積は大きく増やせないけれども、少しでも広く感じられるようにしたい。こう考えた青木さんが取り入れたのが、一定条件を満たせば建築面積に算入されない場合がある「出窓」です。
LDKの西側には、その出窓を活かしたコージーなソファスペースをつくりました。
ソファの背もたれは、床面積に入らない部分。ここを出窓と一体的にするためには、既製品のソファを見つけるのは難しく、できるだけ空間を活用したいことも鑑みて、今回、家具は造作を基本としています。
「建主さんの中には上質なソファをおもちの方もたくさんいらっしゃいます。そうした愛着のある家具をベースに空間づくりをしていくこともあるのですが、今回はシビアな寸法計画が求められたので、ソファは設計し、制作は工務店で手配。ダイニングテーブルは岐阜県岐阜市に工房を構える家具作家・飯沼克起さんに制作してもらいました」(青木さん)
 上写真の格子の室内側にあたるソファスペース。下部は収納になっている。張地はイタリア製の「Caleido / カレイド 」。クッションはIDEE。
上写真の格子の室内側にあたるソファスペース。下部は収納になっている。張地はイタリア製の「Caleido / カレイド 」。クッションはIDEE。
ソファの生地は、イタリア製の「カレイド」。コットンとリネンで織り上げられた美しい発色と柔らかな肌触りが特徴です。色数も多く、住まい手の個性に合わせて選ぶことができます。
ダイニングテーブルは、Yチェアを使うことが決まっていたので、アームの先端が天板にぴったり当たる高さで制作をオーダーしています。
「何がなんでも造作がいい……とこだわっているわけではありません。また造作の際も、工務店での制作や、家具作家さんへの依頼など、コストバランスで決めているところもあります」
#2 経験に基づく定番パーツでつくるキッチン

ふだんからキッチンは造作、という青木さん。愛用しているのは「シゲル工業」のセミオーダー型のステンレスワークトップ。
「シンクには、バックガードをつけたいんです。水がシーリングの奥まで入り込むとイヤですよね。シゲル工業はカウンターの寸法が自由に指定できて、バックガードがつけられるのが気に入っています。あとリーズナブルなのもポイントです(笑)」
カウンター下は大工による造作で、扉は建具屋につくってもらうのが、青木さんのスタンダードです。

レンジフードは幕板を見せないようにカバーを造作。FUJIOH(富士工業)のカスタマイズ型レンジフード「FSA」シリーズが長年の定番で、フードの厚みが35㎜という薄さが気に入っています。
「リーズナブルで機能的。操作部のスイッチも可愛い(笑)。お掃除機能は特についていないのですが、掃除しやすいですよ」。

コンロの壁には、日光化成のインテリアパネル「ヴィンテージトーン」を住まい手に提案しています。
「キッチンパネルってテラテラだったりピカピカしたものが多いのですが、これは仕上げがマットなんです。樹脂系不燃基材の塗装パネルで、キッチン用に抗菌加工を施すこともできる。漆喰や塗装仕上げの壁と一体化して見えながら、清掃性が良いのでおすすめしています。よくよく見ればシールの継ぎ目は見えないことはないのですが、それほど気になりません」

キッチンの水栓の定番は、グローエのミンタ。
「グースネックなどの選択肢もありますが、使っていない時の姿も、スッキリ見えていて欲しくて。住まい手の要望で、先端だけシャワーに変えることもあります」。

ハンガーバーはtoolbox。
「幅はオーダーできますが、タオル1枚がぴったり収まる既製品の400㎜幅を使っています。ステンレスらしい質感とデザインがいいですよね。こういうのは取り付け位置を細かく指示するよりも、自分で取り付けたくなってしまいます(笑)。ビスの台座が小さくて縦型で、存在感が慎ましいのもポイント。場所も、空間も選ばずになじんでくれる。これが横だと、幅が出て見た目にも気になってしまいますから」
3 機能×シンプル×コスパが決め手の洗面ボウル
 1階の洗面所には、DURAVIT (デュラビット)のシンクを採用。フィリップ・スタルクがデザインした、「Starck 3シリーズ」を埋め込みで使っています。
1階の洗面所には、DURAVIT (デュラビット)のシンクを採用。フィリップ・スタルクがデザインした、「Starck 3シリーズ」を埋め込みで使っています。
「やはりドイツの老舗メーカーだけに、プロダクトとしてクオリティが高い。形がコロンとしていて可愛くて、さらに値段がわりとリーズナブルなのも、愛用している理由の一つです」
青木さんが使っているのは、幅560㎜という比較的コンパクトなタイプ。ただし、深さはしっかり140㎜あって、水を溜めることもできます。オーバーフローもポップアップもついているから水の処理能力にも長けており、水返しがデザインされているため水跳ねも防げるのが、気に入っている理由だそう。
 「自分にとっては、まず合理的で機能がしっかりしていることが大事。そして華美な装飾がなく、コストパフォーマンスがよい……というのが、パーツ選びの基準です」。
「自分にとっては、まず合理的で機能がしっかりしていることが大事。そして華美な装飾がなく、コストパフォーマンスがよい……というのが、パーツ選びの基準です」。
このDURAVITの「Starck 3シリーズ」には、ハンスグローエの「タリスE110 シングルレバー混合水栓」を合わせることが多いそう。
「水栓の吐水口が高すぎると、水跳ねしやすくなり、低すぎるとうまく洗えない。これは吐水口の高さが104㎜とちょうどよく、本体自体がコンパクトなサイズ感で、採用することが多いですね」。
#4 既製品に造作を組み合わせた“一石三鳥”のトイレ
 トイレのペーパーホルダーは、TOTOの「一連紙巻器」に造作を組み合わせたもの。
トイレのペーパーホルダーは、TOTOの「一連紙巻器」に造作を組み合わせたもの。
ペーパーホルダーは、華美な必要はなく、シンプルに紙を切れる機能があればいい。
ただし、そのペーパーホルダーを壁にポンと単に取り付けるのではなく、ひと工夫加えて空間になじませるのが、青木さん流の作法です。
この住まいではペーパーホルダーの上にカウンターを造作して、写真や花器などを置けるように。
「そんなちょっとしたことでも、家に愛着をもつきっかけになると思うんです」
さらに、手すりを組み合わせ、動作の負担を減らす心遣いにも満ちています。
「手すりも、世代によってはあると便利ですよね。ただこれみよがしに、ポンと手すりを取り付けても味気ないし、見ているほうも良い気分はしないでしょう。こんな風に造作と組み合わせて建築と一体化する……ということをよくやります。
機能性で選んだパーツを空間になじませる。そのための造作に、デザイン的な意図だけでなく、また別の機能性をもたせる。そんな“一石三鳥”を常に考えています」

#5 光が灯っていない時でも美しい照明器具

「照明は点いていない時も、アクセントとなってほしい。シンプルでありながら、美しく空間に寄り添ってくれるようなデザインを選んでいます」と青木さん。
ダイニングにはルイスポールセンの「ラジオハウスペンダント(2016年VL45ラジオハウスペンダントとして復刻)」を。外側と内側の層は光沢ある透明ガラスを用い、真中の乳白ガラス層をサンドイッチした三層構造です。

「ダイニングはやっぱりペンダントライトがいいですよね。ダイニングテーブルの上に光が灯っていると、あたたかい家族の象徴のように思えます。“トルボー”かこの“ラジオハウス”、どちらかを選ぶことが多いです。いずれも乳白ガラスを使ったタイプを愛用していて、光が灯った時、照明器具がやわらかく発光し、まわりをあたたかく照らしてくれます」

光がもう少し欲しい、というところはブラケットとダウンライトをプラス。
今回初めて使ったのは「NEW LIGHT POTTERY(ニューライトポタリー)」の「SET(セット)」。艶のある釉薬を施した陶器製で、焼き物ならではの質感を味わえます。
 リビングには「white」、2階の個室には「sand beige」を使っている
リビングには「white」、2階の個室には「sand beige」を使っている
〈このコラムで紹介したパーツ〉
・NEW LIGHT POTTERY SET / plate

〈プロフィール〉
青木律典 | デザインライフ設計室
1973年神奈川県横浜市生まれ。2003年日比生寛史建築計画研究所。2005年田井勝馬建築設計工房。2010年青木律典建築設計スタジオ設立。2015年株式会社デザインライフ設計室に改組。
「格子出窓の家」
神奈川県横浜市
敷地面積 111.78 ㎡
延床面積 83.68㎡
構造規模 木造軸組工法 2階建て
竣工年月 2024年6月
設計 青木律典/デザインライフ設計室
施工 幹建設
造園 小林賢二アトリエ
置家具 飯沼克起家具製作所