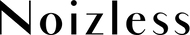【パーツ探訪】 青木律典さんに訊く「住まい手の言葉を膨らませながらつくる ちょうどいい住まいと暮らし」(後編)
建築パーツや建材を切り口に、建築家の設計哲学を浮き彫りにする「パーツ探訪」。後半は、建築家・青木律典さんに「格子出窓の家」の建材や建具、金物を中心にお話をうかがいました。(前編はこちら→)

[プロフィール]1973年神奈川県横浜市生まれ。2003年日比生寛史建築計画研究所。2005年田井勝馬建築設計工房。2010年青木律典建築設計スタジオ設立。2015年株式会社デザインライフ設計室に改組。
#6 四つの役割を担う木製ルーバー

「格子出窓の家」で印象なのが、その名の通りファサード全面に設けられた、木製ルーバーです。
台風をはじめ自然災害が多い昨今、飛んできたモノで窓が割れるリスクを抑えたいという住まい手の要望から生まれたものでした。
もちろん強化ガラスや防犯ガラス、シャッターをつけることも可能ですが、「もう少し建築的な方法を考えたくなって」と青木さんは木製ルーバーのアイデアを膨らませていきました。
飛来物への対策となるだけでなく、厳しい日射の抑制や、外からの視線をやわらげることもできるだろう。さらにその格子を2階まで立ち上げればベランダの手すりにも……と、格子は“一石三鳥”以上の役割を担っています。

「ある一つのことがきっかけになって、複数の効果を生むことができると、すごく嬉しくなるんです」と笑う青木さん。
格子を取り付けることも鑑み、板塀はまちに対して圧迫感を与えないように、低く設けています。
「背の高い板塀って、威圧的になるからあまり立てたくないんですよね。造園家の小林賢二さんが手がけた植栽を、道ゆく人にもみて欲しいと思って」
板塀と格子にはスギを、塗装にはオスモの外装用タイプ「ウッドステインプロテクター」の、3分ツヤの「パティナ」を使っています。
 板塀は内部に支柱を立て、水対策でガルバリウムの笠木を取り付けている
板塀は内部に支柱を立て、水対策でガルバリウムの笠木を取り付けている
#7 やわらかく内と外をつなぐスクリーンの框戸と障子

青木さんが手掛ける住宅でいつも印象的なのが、内外をやわらかくつなぐ、障子や框戸のデザインです。
住宅ごとに微妙にデザインが異なりますが、どのような基準で設計しているのでしょう?
「つくり方は何種類かあるのですが、建主のキャラクターにあわせて、ちょっと縦の組子の本数を増やしたり減らしたり。今回は腰窓なので、上を見上げた時に桟が視界を横切らないようバランスを考えて、デザインしました」
框戸の生地に使っているのは、ロールスクリーンに使うもの。程よく風も抜け、レースのカーテンと同じように昼間は外から見えにくい効果があります。
さらに内側には同じデザインの障子を設けており、夜はこの障子を閉めることで、断熱性や遮音性、プライバシーを確保します。障子紙に使っているのは、ワーロン社の強化障子紙「タフ・トップ」。組子や桟の本数が少なめでも、紙の強度で面が構成できるのも、定番の理由の一つです。
 ここでは框は30㎜、組子・桟は10㎜にしている
ここでは框は30㎜、組子・桟は10㎜にしている
障子と框戸のつくり方は基本的に同じですが、障子が裏から紙を貼るのに対し、框戸は押縁状にして生地を挟み込めるように製作しています。
「やっぱりメインの窓は空間や外としっくりなじませたいので造作します。ただすべての窓でウィンドウトリートメントを造作するのはコスト的にも難しい。適材適所でロールスクリーンやブラインドも採用します」
たとえば西側のデスクスペースの窓は、西日をしっかりと遮る目的でロールスクリーンを。東側のキッチンの窓は、日中作業をしている時近隣の緑がほのかに見えるように、ブラインドを使っています。
 2階のラウンジにも障子を入れている。窓辺にはちょっと腰掛けられるベンチを。下部は収納になっている
2階のラウンジにも障子を入れている。窓辺にはちょっと腰掛けられるベンチを。下部は収納になっている
 障子とガラス窓を開けると、物干し用バーが。建物となじませるため、中から見えにくい位置に取り付けている。錆びにくいステンレス製で、太さは15㎜φ。幅は3.6mでたくさんの洗濯物を干すことができる。布団を天日干しする場合は、1階から立ち上がるルーバーの手すりに掛ける。
障子とガラス窓を開けると、物干し用バーが。建物となじませるため、中から見えにくい位置に取り付けている。錆びにくいステンレス製で、太さは15㎜φ。幅は3.6mでたくさんの洗濯物を干すことができる。布団を天日干しする場合は、1階から立ち上がるルーバーの手すりに掛ける。
#8 玄関扉の金物は可愛らしさと使いやすさと防犯性が決め手
 帰宅のたびに出迎えてくれる玄関は、やっぱり製作したい。
帰宅のたびに出迎えてくれる玄関は、やっぱり製作したい。
玄関はあたたかみのあるピーラーを縦張りとし、間に断熱材をサンドイッチしています。
また内外で5㎝の段差を設けて水切りとし、風対策としてピンチブロックを用いています。
玄関まわりの金物は堀商店のレバーハンドル「LFR」とシリンダー「HORI 1171-64」「オリーブナックル丁番」が定番です。
 「“オリーブナックル丁番”は、ドアを閉めた時に軸の部分(ナックル)だけが見えるタイプで、メンテナンスや交換がしやすいメリットも。デザインが可愛らしいのも気に入っています。
「“オリーブナックル丁番”は、ドアを閉めた時に軸の部分(ナックル)だけが見えるタイプで、メンテナンスや交換がしやすいメリットも。デザインが可愛らしいのも気に入っています。

鍵には、“トライデント®️シリンダー”を使っているのですが、ピッキングや複製が困難な形状で、防犯性能が高いと言われています。ピストルみたいで可愛いですよね。引き渡しの時、建主に渡すと、“コレ、なんですか?”って聞かれます(笑)。
レバーハンドルは堀商店でもさまざまなデザインがありますが、ぼくは横にスッと長い“LFR”が好みです。

#9 素っ気ないほどシンプルなステンレスの平皿の引き手

室内の引き戸に使っているのは、スガツネ工業の「ステンレス 丸戸引手(SMH型)」
「ほんとうにシンプルなステンレスの平皿なんですが、指1本でかんたんに開け閉めできる。要素が極限まで削ぎ落とされて素材だけがある、という感じが好きです。シルバーのメッキをかけた樹脂製だと、ちょっと好みからはずれるんですよね」
サイズは5種類ありますが、青木さんの定番は直径30㎜。
「引き戸はハンガーレールで吊っているので、開け閉めするのにそれほど力はいらないんです。指が、ぐいと入ればよいので、指をあててサイズを試した結果、30㎜に落ち着きました」
 スガツネ工業の「ステンレス丸戸引手」は、ふだんから手元に置いているパーツの一つ。「自分が好んで使うパーツや建材のサンプルがそばにあると、これが取り付くんだ、と思いながら設計できてちょっと安心するんです」と青木さん。
スガツネ工業の「ステンレス丸戸引手」は、ふだんから手元に置いているパーツの一つ。「自分が好んで使うパーツや建材のサンプルがそばにあると、これが取り付くんだ、と思いながら設計できてちょっと安心するんです」と青木さん。
引き戸は、枠も巾木もつけないとのこと。
「巾木にホコリが溜まるのがイヤなので、枠もつけない。ただ、引き戸が壁に当たることを考えて、戸当たり部分の下地には伊藤忠の“地球樹Mクロス”というクロス下地合板を石膏ボードと同じ厚みで入れています。ハンガーレールでストッパーも効くから、多少力を入れて閉めてもトンと当たるだけなのですが、念のために入れています」

#10 見栄えよし、コストよしの複合フローリング

フローリングにはオーク材を使っていますが、LDKは東京工営の複合フローリング「オークEGS自然オイル塗装品」、廊下-階段-2階はオスモの複合フローリングヨーロッパオークA クリア塗装」と使い分けをしています。
「フローリングを選ぶ時、優先順位は“長さ”で決めたいのですね。ただオークは無垢が採れにくくなっていて、幅が狭かったり長さが短かったりということがあるんです。
張った時の見栄えが変わってきますから、やはりそれなりに寸法は欲しいのですが、コストが合わなくなってくる。ただ、コストを抑えようとすると乱尺など選択肢が狭まってしまいます。
そんな時に見つけたのが、オスモの“D40”。幅148㎜×長さ1820㎜というサイズを使っているのですが、コストパフォーマンス的な面でも使いやすくていいですね」と青木さん。

階段にも“D40”を使っていますが、段鼻の処理に青木さんらしい工夫が見て取れます。
「複合フローリングはどうしても小口が見えてしまいますよね。LDKから廊下、そして階段の壁も含めてトータルで無垢材のように見せたいという意図がありました。そこで段鼻を踏面よりも1ミリ上げて取り付けることで、小口を隠すとともに、滑り止めにもなる納まりにしています」
 複合フローリングの小口を隠しつつ、ノンスリップにもなる段鼻。段板には1段分を2枚で収めるように、大工が加工している
複合フローリングの小口を隠しつつ、ノンスリップにもなる段鼻。段板には1段分を2枚で収めるように、大工が加工している
 階段の側壁には、東京工栄の「アルダーSパネル」。最大長さ2.7mで、上下を落として納めている。マットな白い塗料でツヤを抑えている
階段の側壁には、東京工栄の「アルダーSパネル」。最大長さ2.7mで、上下を落として納めている。マットな白い塗料でツヤを抑えている
紙のカタログをめくっていて得られるひらめき

パーツや建材を探すのは楽しい、と語る青木さん。膨大な数のなかから選ぶ基準はどこにあるのでしょう。
「自分が設計する空間に違和感なくなじむものを選びたいと思っているのですが、その時に、“機能的”、“華美でないこと”、“コスト”という視点でふるいにかけます。
機能的であることは大前提で、さらに美しさを感じられるとよい。ただデザインが主張しすぎるのはちょっと困る。そしてやはり金額が適正であるか、ということですね」
パーツを自らつくりたい、と思われることはないのでしょうか?

「家具は必要に応じて造作しますが、パーツは、既製品をうまく生かしながら、理想の空間に近づけていくというスタンスです。それが楽しい、と思っているんですね。もちろんオリジナルでプロダクトやパーツをつくることも魅力的ですが、やはり費用対効果でどうなのかな、と。住宅1軒1軒のために、ものすごいお金を投入して部分にこだわるよりも、全体のバランスが取れているほうがよい。となると、結果的に既製品のなかから良いものを選んで、それを組み合わせながら、良い空間をつくっていく……ということになります」
そんな青木さんは、カタログ見るのが大好きだそう。ただしカタログはオンライン派ではなく、「紙」派とのこと。なぜそこにこだわっているのでしょう?
「紙のカタログをペラペラとめくっていくなかで、これってこんな風にも使えるんじゃないか、など、ふと閃くことがあるんですよ。はじめから目的が決まっていて探す場合はウェブでも事足りるのですが、目的なくカタログをめくっている時に、思いついたり発見することがある。そんな時間を大切にしています」
立体的なパズルがぴったりとはまる瞬間

そんなパーツ選びの先にある空間づくりは、どのように考えているのでしょう。
「建築をつくる時に、あらかじめ確固としたイメージがあるわけではないんです。“ちょうどいい住まいと暮らし”をつくりたいと心がけているのですが、“ちょうどいい”って人によってまったく違ってきますよね。敷地条件も家族構成も要望も予算も価値観も異なりますから。なので、その人にとって“ちょうどいい”ことは何か……を一緒に考えながら、家づくりをしたいと思っているんです。設計という仕事、というより活動や生業(なりわい)に近いのかもしれないですね」
「なので、建築家として自分がこういうものをつくりたい、というわけではなく、建主と話していくなかで、印象に残る言葉を掬い上げ、特徴を見出して、建築をつくっていくという方法論です。建主も自分が言ったことが形になって現れた、と共感してくれることが多いように思います」
 さまざまな言葉や切り口で語られる理想の住まい像。設計は、その断片を一つひとつ組み合わせたり、膨らませたりするプロセスでもある、と青木さんは語ります。
さまざまな言葉や切り口で語られる理想の住まい像。設計は、その断片を一つひとつ組み合わせたり、膨らませたりするプロセスでもある、と青木さんは語ります。
「さまざまなピースが最終的にバチっとはまるというか、これしかない……という瞬間があるんですよね。それが、“ちょうどよい”ということだと思っています」

青木さんにとってのノイズレスってなんですか?
「建主からもらった感想で、いくつか共通していることがあるんです。できあがった家を見ると気になるものが何もない、というもので、目に優しい、というような言われ方をしたこともあります。それがまさにノイズレスな状態なのではないでしょうか?」
住宅はさまざまな建材やパーツの組み合わせでできあがるものなので、ノイズがないはずはないけれども……と前置きしたうえで、青木さんは、こう続けます。
「やっぱり自分の意識としては、そうした組み合わせによって発生するノイズを抑えるような、モノの選び方や空間設計をしているのかな、と思いました。自分が目指しているのもそのような状態ですし、建主から前述のようなことを言われると、充実感があるというか、まさにこういことがしたかった……と思えるんです。自分にとってノイズレスとは、そんな位置付けですね」

〈このコラムで紹介したパーツ〉
オスモ 複合フローリングD40 ヨーロッパオークA クリア塗装

【プロフィール】
青木律典/デザインライフ設計室
1973年神奈川県横浜市生まれ。2003年日比生寛史建築計画研究所。2005年田井勝馬建築設計工房。2010年青木律典建築設計スタジオ設立。2015年株式会社デザインライフ設計室に改組。
「格子出窓の家」
神奈川県横浜市
敷地面積 111.78
延床面積 83.68㎡
構造規模 木造軸組工法 2階建て
竣工年月 2024年6月
設計 青木律典/デザインライフ設計室
施工 幹建設
造園 小林賢二アトリエ
置家具 飯沼克起家具製作所