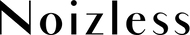【パーツ探訪】丸山 弾さんに訊く「風景と響き合う空間設計の作法」後編
建築パーツや建材を切り口に、建築家の設計哲学を浮き彫りにする「パーツ探訪」。後半は、建築家・丸山弾さんに「つくばの家」の建具や外部のしつらえを中心にお話をうかがいました。(前編はこちら→)

[プロフィール]丸山弾:1975年東京都生まれ。1998年成蹊大学卒業。2003年堀部安嗣建築設計事務所入所。2007年丸山弾建築設計事務所設立。2022年丸山弾-スタジオに改称。2007〜2024年京都芸術大学大学院非常勤講師、2024年より日本大学芸術学部非常勤講師。
#7 街中になじむグレーの杉板の外壁

杉板張りの外壁は、住まい手の要望も受け、グレー系の仕上げにしています。しかしひと口にグレーといっても幅が広く、使用する樹種によっても色の仕上がりは大きく変わります。今回はやや赤みを帯びた八溝杉(茨城県北部から栃木県那須地域にかけて産出される杉)を使用し、仕上げにはドイツ製の自然塗料「プラネットカラー」を採用しました。
グレーという選択は、街中で木の外壁を使ううえでもうってつけ。
「林の中では、木を素地で使うことが多いです。経年変化で周辺の木の幹の色と馴染んでいきます。しかし街中では木を素地で使うより、着色したほうが周辺の街並みに馴染むと思っています」

「プラネットカラーは、大宮にあるショールームに板を持ち込めば、その場で調合して、試し塗りをしてくれます。つくばの家では、20パターンほど色調を試して、現地の光の下でこの色に決定しました。経年で、色が変化していくことを予測しておくことも大切です」
#8 ストレスフリーの洗い出しのアプローチ


玄関アプローチに選んだのは、洗い出し。
「コンクリート、モルタル、石、タイル……外部アプローチの素材にはさまざまな選択肢あります。洗い出しの良いところは、目地がなく方向性が出ないということと、土の汚れが目立ちにくい。そしてクラックが目立ちにくいという、三点でしょうか」と丸山さん。

アプローチの入り口から、クランクして玄関扉があります。このときに石やタイルなど目地が入る素材にすると、目地の方向性により、アプローチの入り口をメインにするのか、玄関扉をメインにするのかのどちらかになります。ここでは、両方ともメイン。そのため、方向性が出ない洗い出しにしています。
「おおらかに暮らせるのが、何より大事だと思っています。そこが担保できていれば、“この素材でなければならない”という線引きは特にありません。空間の邪魔をしない範囲で、手に入りやすくて丈夫なものなら良いというスタンスです」

モノには偏ったこだわりをもたない代わりに、丸山さんが心がけているのが、「徹底的に設計で線を引く」ということ。図面の段階で、どんな空間をつくりたいか、それらはどんな関係性にあるのか、ということを追究します。
「設計の段階で、空間の輪郭や関係性を整えていくのですが、もちろん前提として、各素材が空間に与える影響を考えています。そのため、諸事情で現場の段階で素材が変更になると、整え直すのにひと苦労します」
 ドアのレバーハンドルは、堀商店の「MCR(BY)」が定番。座は小さいタイプ。円筒形シリンダー錠にディンプルキーを組み合わせるが、ピッキングに強いので防犯対策の面でも信頼できる。
ドアのレバーハンドルは、堀商店の「MCR(BY)」が定番。座は小さいタイプ。円筒形シリンダー錠にディンプルキーを組み合わせるが、ピッキングに強いので防犯対策の面でも信頼できる。
#9 「建築と一体」で考える木製建具

庭と暮らしをつなぐリビングの窓は、床板と木製のテラスに連続性をもたせたいところ。窓を既製品にすると枠や框の樹脂や金属で、木の連続性が途切れてしまうので、木製建具を採用しています。
構成は、中央を出入り口とし、その左右にFIX窓を設けるというかたちに。気密性を担保するため、出入りや採風のための開口部は1カ所で十分、そして両引きではなく片引きに……という発想です。
丸山さんが木製建具にこだわるのは、「建築と一体」のものとしてつくれるため。窓を既製品にすると、とかく空間において線が増えてしまいますが、建築と建具を一体で考えることで、余計な線を極力減らしたり、方立(ほうだて)と框(かまち)の寸法を合わせて開口部全体をすっきり見せることができます。

ウィンドウトリートメントは、ボックス内に二重のロールスクリーンを。内側に光を透かすレース、窓側に遮光性のある生地を用いています。サイズの大きい二重のロールスクリーンを取り付けるため、ディテールはひと工夫したとのこと。
「ふだんはロールブラインドのシングル使いか、障子を採用することが多いですね。今回は、庭の気配を程よく感じたい時と、光や外からの視線をしっかり防ぎたい時、両方に対応できるようにするため、2重にしています。ちなみに水回りなどの窓にはアルミブラインドを使いますが、幅が狭いタイプ(15㎜)を使います。シャープに見えて、光もきれいに見えます」
ロールスクリーンは「タチカワブラインド」の「ラルクシールド」を採用。
木製建具は気密性を確保するため、戸じゃくりを取って建具を納め、戸先にはピンチブロックを入れて、他の三方はモヘアで気密を補う。隠し框は、框の重なりを深く取る納まりにして、モヘアを設けるスペースも確保しやすくしている。框が隠れることで、線が減り、外への視線が抜けやすくなる。テラスとは段差が生まれるが、外用のスリッパがちょうど隠れる高さに。外から見た時も定木(じょうぎ:枠まわりに取り付ける見切り材)が見えにくくなり、外観もすっきり見えるというメリットもある。
#10 さりげなく空間に溶け込むアルミサッシ

木製建具の良さを語る丸山さんですが、現実的に家の建具をすべて木製で制作するのは難しく、またエリアによっては防火対策を講じる必要もあります。そのため既成のサッシを使う場合、窓台を上げて枠を隠し、空間になじませる工夫を施しています。

「小さな窓の場合、既成のサッシの方がすっきり見えて、視線が外に抜けやすいことがあります。コストや将来的な管理も踏まえた上で、目的に応じて、窓の種類は決めています」
 2階の子供部屋。本棚の向こうが吹抜けのLDK。
2階の子供部屋。本棚の向こうが吹抜けのLDK。
#11 木の天井で交換型照明使うひと工夫
 小口は6㎜、目地は4㎜としている。
小口は6㎜、目地は4㎜としている。
「照明カタログってものすごく分厚いですよね。けれどもソケット交換型の照明が、いまやかなり少なくなっています」と苦笑する丸山さん。
最近の照明器具はLED一体型が主流ですが、切れると電気工事が必要になり、業者に頼まなければならず、一大事に。丸山さんは住まい手が自分で取り替えられるソケット型(ランプ交換型)のタイプを愛用しています。
以前は木を張った天井の時は、なじみのよいシルバー枠のダウンライトを使っていたものの、それも廃盤になってしまったとのこと。なんとか交換可能なソケット型の電球を使いつつ、照明の存在感を抑えられないかと考えて行き着いたのが、造作で照明ボックスを制作するという発想です。

天井をシナ合板張りとした2階の寝室。

動くものを眺める時間が、暮らしを豊かにする
〜庭、そして街というランドスケープと響き合う

空を流れる雲や、風に揺れる枝や葉影──「つくばの家」の窓からは、自然の豊かな営みを眺めることができます。
「人間って、自然と動くものに目が行きます。一つの場所で長居をすることができるのも、動くものが見えるから、飽きない。飽きないからその場にいられる。そういった場所が“居場所”につながると思っています。そして、自分も動きます。顔を振り向けた先にも視線が抜けて、その先に動くものがあるとより飽きず、長居できると思っています」
京都で教鞭を執っていた丸山さんは、仕事で京都に通う際、さまざまな古建築を巡るのが楽しみだったと言います。
「たとえば石庭で有名な龍安寺は、長居をしている人たちが多いのです。石自体には動きはないのですが、庭の奥にある土塀の上の樹木が風で揺れています。庭に落ちた木の影も揺れています。視線の先に、動くものがあるから、その場が飽きず、長居ができるのではないでしょうか。静かなものと動くものが同居していることも、お互いの良さを引き出していると思います」

しかし今、住宅の間取りはそうした“動くもの”を意識しない方向になっている、と丸山さんは語ります。
「住宅の歴史を振り返ってみると、テレビが出現する前は、茶の間に座って、縁側越しに庭を眺めていましたよね。庭は風や雨で動くので、眺めていても飽きない。ところがテレビが登場すると、庭ではなく、テレビに目線が行くようになりました。あるいはLDKの時代になって、ソファは庭ではなく、テレビに向かってレイアウトされるようになりました。そして庭は駐車場になり、カーテンが閉められることに。現代はそのレイアウトの中で、テレビではなく、手元のスマートフォンを見ているが現状です。住まいの内と外が、分断されてしまいました」
視線の先に何があるのかという考えを育むに至ったのは、丸山さんの原体験も影響しています。
「生まれ育ちは東京・中野で、曲がりくねった細い道のまわりに家がひしめきあっている……という環境です。そして神田川の近くで、坂道の多い地形でした。坂の上にのぼるとすっーと視線が抜けるのが好きでした。なので住宅を設計するときも、居場所からすっーと視線が抜けることを心がけています。都心部の家でもそこから考えていきます」

丸山さんにとってのノイズレスってなんですか?
丸山さんが大切にする内外の関係性は、住宅の敷地内だけで完結せず、その先の街並みや風景までを見据えたものです。
「自分にとってのノイズレスというのは、建築の納まりや空間性の話だけではなく、周辺の家や街並みと自然に調和した状態のことだと思います。そのためには、街中でも郊外でも林の中でも、それぞれの土地の形状や気候風土に合った建築をつくることが大切だと考えています。
さまざまな地域で設計の機会をいただいていますが、その土地で育まれた屋根の形や素材から謙虚に学んで、活かしていけば、自然と昔からそこに建っていたような佇まいになります」

「かつての家づくりは、その土地の素材を使い、その土地の気候に合わせて屋根の形を決めていたものでした。今は物流と建材の発達によって、日本中どこへ行っても同じような家が並んでいますが、かつての家づくりにあった“土地に学ぶ姿勢”を大切にしたい」
大学を卒業して、渡欧した時に出会ったのが、ストックホルムにある北欧建築の巨匠グンナール・アスプルンドの「森の火葬場・森の墓地」。この場所に心を打たれて、ランドスケープと響き合うものをつくりたくなった、と語ります。

「景観は、自然景観と人文景観(*)に分かれますが、建築は人文景観に含まれます。家は個人のものであるとともに、誰の目にも入り込む景観の一部でもあります。街を共有する意識が少なくなっている現代だからこそ、あえて、その垣根や境界線をルーズにしたい。今は時代的にも高断熱・高気密が求められ、その意味でも、外とのつながりが希薄になりがちです。開口部の大きさや数、性能値で制限を受けたとしても、やはりしっかり外とは繋がりたい。その先に、心地よい家、そして心地よい街並みが生まれると思っています」
*人文景観=人間が自然環境に働きかけ、長年の生活や文化活動を通して作り上げてきた景観のこと

〈このコラムで紹介したパーツ〉
・プラネットジャパン「プラネットカラー」
・タチカワブラインド 「ラルクシールド」
・堀商店 レバーハンドル 「MCR」
・堀商店 取手「430-B」
・フォンテトレーディング 磁器質タイル「G400」
・ストーブ工房 山林舎
【プロフィール】
丸山 弾 / 丸山弾建築設計事務所
1975年東京都生まれ。1998年成蹊大学卒業。2003年堀部安嗣建築設計事務所入所。2007年丸山弾建築設計事務所設立2022年丸山弾-スタジオに改称。2007〜2024年京都芸術大学大学院非常勤講師、2024年より日本大学芸術学部非常勤講師。
「つくばの家」
茨城県つくば市
敷地面積 366.39㎡
延床面積 121.46㎡
構造規模 木造軸組工法 2階建て
竣工年月 2022年4月
設計 丸山弾(丸山弾-スタジオ)
施工 けんちく工房 邑
造園 舘造園