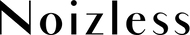【パーツ探訪】比護結子さんに訊く「 暮らしが入って完成するものだから建築は少し引き算気味に」(後編)
建築パーツや建材を切り口に、建築家の設計哲学を浮き彫りにする「パーツ探訪」。後半は、建築家・比護結子さんに「さうさうのいえ」で、素材や構造的な試みについてお話いただきました。 (前編はこちらから)
 リビングから1.2m下のレベルにあるダイニング・キッチンを見下ろす。レベル差のある場所を一体的な空間にするため、緑地が見える西面に連続する水平窓を設けた。「既製品でもプロポーションの良いものを使えば、きれいな連続窓がつくれます」と比護さん。
リビングから1.2m下のレベルにあるダイニング・キッチンを見下ろす。レベル差のある場所を一体的な空間にするため、緑地が見える西面に連続する水平窓を設けた。「既製品でもプロポーションの良いものを使えば、きれいな連続窓がつくれます」と比護さん。
 階段を上がった先のリビング。壁を背にして落ち着きを感じられるが、視線は緑地に向かって抜けていき、開放感も味わえる。東側(左手)の壁に対して西側(右手)の壁は斜めに広がっていくような間取りになっている。
階段を上がった先のリビング。壁を背にして落ち着きを感じられるが、視線は緑地に向かって抜けていき、開放感も味わえる。東側(左手)の壁に対して西側(右手)の壁は斜めに広がっていくような間取りになっている。
#6 ノスタルジーを宿すおおらかなラワン材

建築を特徴づけるうえで重要なのが、屋根と天井。比護さんが手がける住宅でも、いつも屋根と天井が印象的です。
「さうさうのいえ」で架かっている屋根は、単純な切妻ではありません。
平面には長手方向に軸が2本あり、南から北に向かって広がるような形状に。さらに北と南は高さが異なる複雑なかたちになっています。
 比護結子さん:愛知県豊田市生まれ。奈良女子大学家政学部住居学科卒業、東京工業大学大学院修士課程修了。1999年、柴田晃宏と一級建築士事務所ikmo設立。桑沢デザイン研究所非常勤講師(2005-2025)、芝浦工業大学非常勤講師(2012~)などをつとめる。「キチ001」(東京建築士会住宅建築賞)、「cotoiro」(グッドデザイン賞2015)、「おかやまのいえ」(第9回JIA中国建築大賞住宅部門優秀賞)、「椿庵」(「千葉県建築文化賞」住宅部門最優秀賞)、「さうさうのいえ(千葉県建築文化賞・住宅部門 最優秀賞)」などを受賞。
比護結子さん:愛知県豊田市生まれ。奈良女子大学家政学部住居学科卒業、東京工業大学大学院修士課程修了。1999年、柴田晃宏と一級建築士事務所ikmo設立。桑沢デザイン研究所非常勤講師(2005-2025)、芝浦工業大学非常勤講師(2012~)などをつとめる。「キチ001」(東京建築士会住宅建築賞)、「cotoiro」(グッドデザイン賞2015)、「おかやまのいえ」(第9回JIA中国建築大賞住宅部門優秀賞)、「椿庵」(「千葉県建築文化賞」住宅部門最優秀賞)、「さうさうのいえ(千葉県建築文化賞・住宅部門 最優秀賞)」などを受賞。
6つのレベルの異なる床をまとめあげる天井は、厚5.5㎜のラワンベニヤ張り。おおらかにスキップフロアをつなぐため、継ぎ目を目立たせないように配慮して張り、家具や建具と色味を合わせるためオイル塗装で着色しています。
そのラワンは比護さんが好む素材の一つで、キッチンのフードやライブラリーなど、随所に使われています。
「ラワンのおおらかな印象や、どこか昭和を思い起こさせるノスタルジーを宿す雰囲気が好きです。表情も豊かで、面として使いやすい。床にもラワンを使うこともあります」
 キッチンのフードの幕板をラワンランバーコアでつくり、天井と一体感を生む。
キッチンのフードの幕板をラワンランバーコアでつくり、天井と一体感を生む。
#7 建具は隠さず素直に潔く見せる

ダイニングの片側は大勢が座れるベンチであり、下部は収納、さらに階段へのステップともなる。右手の扉の奥は洗面とトイレ。その上は隠れ家のようなロフト。テーブルもオリジナルで製作。
建具は壁と同面(どうづら)にすると、開け閉めで壁部分が凹んで見えてしまう。
建具の存在は消せないので、だったら壁に1枚の板がくっついているように素直に見せたい……と語る比護さん。
ダイニングキッチンの東側、洗面とトイレの建具も、その言葉通りに素朴な存在感で空間に溶け込んでいます。
この納まりにはコツがあり、振れ止めに使うハンガーレール用のガイド金物を、本来の建具の下端ではなく上に取り付けているということ。
「当初は金物を製作していたのですが、職人さんに、“あの金物、転用できるよ”と教えてもらって。ただ気密をしっかり確保しなければならない時は、上部に鴨居を入れることもあります」

建具の下部に取り付けるガイド金物を上部に使い、開け閉めする
#8 窓周りをすっきりさせる埋め込み式カーテンレール
 カーテンにヒダが多いと重苦しく見えてしまうこともあるので、フラットカーテンを採用したい。ただし、端に寄せた時に前後に大きく畳まれてしまうので、納まりが良くないのが悩ましい。
カーテンにヒダが多いと重苦しく見えてしまうこともあるので、フラットカーテンを採用したい。ただし、端に寄せた時に前後に大きく畳まれてしまうので、納まりが良くないのが悩ましい。
そんな比護さんにとって、カーテンレールの定番の一つが、TOSOの「シエロライン」です。
「埋め込み式で窓周りをすっきり見せられるだけでなく、リングランナーのヒートン部分が回転するので、ヒダ(タック)が少ないカーテンを使っても、スムーズに畳めます」
比護さんがふだん使うのは、「つば」が出ないタイプで、埋め込みやすくて施工しやすいのが気に入っている理由です。

「カーテンは窓の外側に付けることもあります。内側だとカーテンを左右どちらかに畳んだ時、畳んだカーテンに窓が塞がれる分だけ、景色が狭く見えてしまいますよね。わずかな差かもしれませんが、コンパクトな住宅では窓が少しでも広く見えたほうがいいと思っています」

#9 軽やかに宙に浮く無柱の鉄骨バルコニーとシンプルな庇
 布団など大きな洗濯物を天日干しするために設けたバルコニー。
布団など大きな洗濯物を天日干しするために設けたバルコニー。
「コスト調整もあるので基本的には既製品をうまく使いたい。ただ、既製品で物足りない場合はつくります」という比護さんが今回製作したのが、リビングとダイニングキッチンの前の鉄骨のバルコニーと、地下室の庇です。
リビングとダイニングキッチンの西側には、水平連続窓に沿うように、幅5.5mの鉄骨バルコニーを設けています。

柱を立てずに軽やかで素朴な存在にしたい、と、あたかも1枚の鉄板が宙に浮いているようなつくりに。
床には溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)の鋼板(チェッカープレート)を使い、チャンネル(溝型鋼材)とフラットバー(平鋼)によって支えていますが、下から見上げても端正に見えるように考慮したところ。
両サイドの丸鋼の斜材とともに、鉄骨の構造は本体の木構造とボルトで緊結し、ボルトが目立たないように工夫しています。

「裏側をいかにデザインするか、ということは注意を払いました。きれいに見せたかったので、100㎜の厚さで納まるように構造家とともに考えました。またドブ漬けの鉄骨を1体で製作するのが困難だったので、施工者と構造家と3者で話をしながら詰めていきました」

地階の庇は、外壁から1枚の板が取り付いているかのようにシンプル。
外壁の内部でボルト留めにしていますが、下から見えない位置にリブを溶接してあり、垂れない工夫を施しています。

#10 凹凸でスケール感を表現するガルバリウム鋼板の中波

外壁には、ガルバリウム鋼板の一文字葺きか波板を採用することが多いという比護さん。
小波板だと厚みがやや物足りなく、中波のつくる陰影が好み、とのこと。
「小さい住宅は素材のスケール感も大事だと考えており、既製品のサッシや雨どいを使う場合、繊細な小波だとスケール感が合わないと感じることも。小さい家だからといって、見た目が繊細なものを使うのではなく、ちょっとイレギュラーにするのも一つの手だと思います」
コーナーにはカバーを取り付けず、内側に止水用の板金を入れてシールで留めています。

小住宅でもおおらかで素朴
建築のルーツは学生時代に調査した民家にあり
 おおらかな空間と、素朴なパーツの存在感。
おおらかな空間と、素朴なパーツの存在感。
そんな比護さんの建築に影響を与えたのが、「民家」です。
「学生時代に民家の研究をしていたのですが、どの民家も似ているようでいて、実は調査すると1軒1軒異なるんです。民家は、地域の技術や風土に合ったつくり方や素材のなかで、暮らしだけでなくつくる人の工夫もあるので、それぞれの工夫が折り重なってできているものなのですね」
「だから民家は統一感のある街並みをつくりながら、近くで見たり、触れると一つひとつ面白い。そういう奥行きがあります」
「現代では、家の価値を間取りや床の広さで測るところもありますが、『間取り』は、どこか、神の目線のようなもの。子どもや動物は、間取りのことは気にしないですよね」
設計では平面よりも断面を先に考えるのがセオリーで、特に『さうさうのいえ』では、地形を再構築する目的もあり、断面計画を重視したとのこと。

「断面から先に考えるのは、小住宅を手掛けることが多い、という理由もあるかもしれません。
小住宅では広さをシビアに考えなければなりませんが、広さに対する感覚は、人によって違います。なので住まい手の方には、何をしたいですか?と聞いて、広さを決めていきます。
たとえば読書をしたいのか、ヨガをしたいのか。その答えによって、必要な床の広さは違ってくる。床が小さくても窓の外へ視線を抜いたり、高さを調整したりして、実際の床面積以上に広く感じるように……というつくり方をします。
目線や光のことを考えていくと、やはり断面から先に考えたほうが、自由が効くのです」
好きなのは、素朴で可愛く機能的なパーツ
 設計から転じてパーツの好みについてうかがうと、返ってきたのは「素朴で可愛く機能的なものたち」という答え。
設計から転じてパーツの好みについてうかがうと、返ってきたのは「素朴で可愛く機能的なものたち」という答え。
「昭和の時代にエンジニアリングの延長でつくられたようなパーツが好きです。アノニマスで民家にも共通する素朴さがあり、デザイナーが考え抜いて出来上がったパーツより、空間との相性が良い。『素』である良さは、さまざまな住宅に合う、ということでもあります。そして特定の家にしか合わないのではなく、他の家でも使いやすいものが定番になっていきます。ただ、そうしたものが最近、廃盤になっていくことが悩みです(笑)」
 住まい手が取り付けた小物。パーツに対する価値観は住まい手とも共有。
住まい手が取り付けた小物。パーツに対する価値観は住まい手とも共有。
比護さんにとってのノイズレスってなんですか?
 「暮らしの中で起こることや外部の自然は、取り込みたい“ノイズ”です。ただ、建築自体のノイズはコントロールしたい」
「暮らしの中で起こることや外部の自然は、取り込みたい“ノイズ”です。ただ、建築自体のノイズはコントロールしたい」
素材同士の継ぎ目をなくしたり、空間をシームレスに連続させたり。ただ、あまりに作為的になると、そのこと自体がノイズになってしまう、と比護さんは語ります。
「たとえば小口を隠そうとすると、建築側からの要求が一つ増えますよね。隠そうとすることで要素が増えるのなら、スパッと切って潔く見せる。建具は隠し框にはしないけれども、要素を減らして素朴に見せる……といった具合でしょうか」
「住宅の場合、出来上がった時、空間がちょっと寂しいかな?というくらいのほうがいいと思っています。
住宅は人とモノが入って完成するので、建築のほうでつくり込み過ぎると、ちょっとうるさくなってしまう。
住まい手の方が自分でつくってみたり、工夫してくれるとうれしいですね」

気持ち良い場所はネコが教えてくれる
心がけるのは、体感を大事にした建築

「さうさうのいえ」には3匹のネコがおり、階段や窓辺など、めいめいが好きな場所で気持ちよさそうに過ごしています。
そんな猫たちの様子に目を細める比護さんも愛猫家。ペットと暮らす住まいの設計にも定評があります。
 「ネコの暮らし方は住空間をつくるうえで参考になります。季節ごとにいちばん気持ちのよい場所で寝ていますよね(笑)。住まい手の方にも、その時々の体感で、居心地の良い場所を探してもらえればと思います。ごはんだって、必ずしもダイニングでなく、気持ち良ければ階段で食べてもいい。空間って、そんなふうに使われるべきではないでしょうか」
「ネコの暮らし方は住空間をつくるうえで参考になります。季節ごとにいちばん気持ちのよい場所で寝ていますよね(笑)。住まい手の方にも、その時々の体感で、居心地の良い場所を探してもらえればと思います。ごはんだって、必ずしもダイニングでなく、気持ち良ければ階段で食べてもいい。空間って、そんなふうに使われるべきではないでしょうか」
<このコラムで紹介したパーツ>
【プロフィール】
比護結子
愛知県豊田市生まれ。奈良女子大学家政学部住居学科卒業、東京工業大学大学院修士課程修了。1999年、柴田晃宏と一級建築士事務所ikmo設立。桑沢デザイン研究所非常勤講師(2005-2025)、芝浦工業大学非常勤講師(2012~)などをつとめる。「キチ001」(東京建築士会住宅建築賞)、「cotoiro」(グッドデザイン賞2015)、「おかやまのいえ」(第9回JIA中国建築大賞住宅部門優秀賞)、「椿庵」(「千葉県建築文化賞」住宅部門最優秀賞)、「さうさうのいえ(千葉県建築文化賞・住宅部門 最優秀賞)」などを受賞。
「さうさうのいえ」
千葉県市川市
敷地面積 86.12㎡
延床面積 82.85㎡
構造規模 木造+RC造、2階建て
竣工年月 2023年7月
設計 一級建築士事務所ikmo
施工 株式会社中野工務店