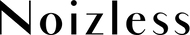パーツ探訪 「森田悠紀さんに訊く 旬の食材を料理するように設計する」(後編)

建築パーツや建材を切り口に、建築家の設計哲学を浮き彫りにする「パーツ探訪」。後半は、建築家・森田悠紀さんに「国分寺の家」でオリジナルの製作パーツを中心にお話いただきました。 →前編はこちら
 森田悠紀
森田悠紀
1984年静岡県生まれ。2007年千葉大学工学部デザイン工学科建築系卒業。2007〜2008年リスボン工科大学建築学部。2009年千葉大学大学院工学研究科建築都市科学専攻修了。2009〜2012年株式会社小川広次建築設計事務所。2013〜2015年株式会社ワークヴィジョンズ。2015年森田悠紀建築設計事務所設立。2020年〜愛知産業大学非常勤講師。2022年〜千葉大学非常勤講師
#6 貼り方を使い分けた
サバ杢の突板
 サバ杢突板を横使いにしたデスク
サバ杢突板を横使いにしたデスク
ダイニングの階段側のコーナーには、隠れ家のようなデスクスペースが設けられています。
そこで使っているのが、ユニークで美しい木目をもつ、「サバ杢」(マホガニー)の突板。多種多様なストックを持つ突板屋の山一商店の倉庫へ出向き、選んだ素材です。
サバ杢とは、木の幹が二股に分かれて成長する過程で付け根部分に生じるもの。年輪の密度が不均一で個性的な表情を放ちます。
突板でありながら厚みは0.6㎜ほどで重厚感があり、ヴィンテージの家具やラワンともしっくり合うのも、採用した理由の一つです。デスクと幕板、そしてダイニング東側吹き抜けの手すり壁に使うことを決めましたが、サバ杢は採れるサイズが限られることもあり、使い方を熟考。
縦使いにするか横使いにするか、パターンを検証したうえで、デスクと幕板は横使いに、吹き抜けの仕切り壁は縦使いとしています。
いずれもヴィンテージ家具が置かれた時に、建築の一部である造作デスクや手すり壁が、置き家具の仲間のごとくに見えるように逆算して設計したものです。

サバ杢を縦使いにした階段吹き抜け側
 突板材料と割り付け指示(提供:森田悠紀建築設計事務所)
突板材料と割り付け指示(提供:森田悠紀建築設計事務所)
#7 建築と家具をシームレスにつなぐ
半円形のエレメントとディテール
 フォーカルポイントともなる階段周り。階段上部にも半円状のデザインを用いることで、人を招いて、登っていきたい、と思わせるような雰囲気に
フォーカルポイントともなる階段周り。階段上部にも半円状のデザインを用いることで、人を招いて、登っていきたい、と思わせるような雰囲気に
「国分寺の家」を体現するディテールの一つが、半円状の見切り材。
「#6・サバ杢」のデスクにも採用されていますが、こうしたディテールを、韻を踏むように家全体に通底させることで、どこにいても、同じ一つの建築にいるのだという実感を確かなものにしています。
階段の段鼻も同様で、ナラの半円状の見切り材を取り付けています。
デザインのインスピレーションは、テーブルや椅子の丸脚や、天板の小口のアール形状、住まい手が所有するモダニズム期のヴィンテージ家具のデザインやディテール。丸みを帯びたおおらかな雰囲気や、厚みを感じさせるデザインに着想を得ています。
 階段材、見切り材にもナラを採用。ノンスリップの溝は両端まで突き切らず、小さなアールを描くように壁から少し離れたところで止めている
階段材、見切り材にもナラを採用。ノンスリップの溝は両端まで突き切らず、小さなアールを描くように壁から少し離れたところで止めている
階段の滑り止めのために踏面(ふみづら)にノンスリップのミゾを掘るのも一つの方法ですが、今回は半円形の見切り材を踏面に対してわずかに段差を付けて設置し、見切り材の端部にアールの溝を掘ることで、滑り止めとしています。こうした機能的に必要となる要素を見つめ直し、適切に形にすることによって意匠的にもこの住宅のキャラクターをつくることができました」
 右手の窓枠は平面的に斜めに傾けて奥行きをつくり、借景となる隣家の樹木へ目線を絞る。階段の手すり壁の上部にも半円状のモチーフを採用。建築と家具を繋ぐ中間的なスケールのエレメントとしてデザインした
右手の窓枠は平面的に斜めに傾けて奥行きをつくり、借景となる隣家の樹木へ目線を絞る。階段の手すり壁の上部にも半円状のモチーフを採用。建築と家具を繋ぐ中間的なスケールのエレメントとしてデザインした
 弧を描く階段まわり。窓台のディテールにも踏襲されている
弧を描く階段まわり。窓台のディテールにも踏襲されている
 人を優しく迎え入れるような半円形状の玄関框
人を優しく迎え入れるような半円形状の玄関框
#8 手の形になじむ
無垢の木の手すり

手に吸い付くようになじむ形状の手すりは、オリジナルで製作。半円状の見切りなどこの家のモチーフと調和を取りながら、機能的なデザインをめざした結果、生まれました。
製作にあたっては、粘土を捏ねながら原寸で検討し、つくった形を紙に起こしてから製作しやすい寸法に調整するというプロセスをとっています。ある程度の寸法を設定したうえで、何度も図面を出力して、原寸模型と原寸図面の誤差を埋めていく方法を取っています。
「この住宅に置かれているヴィンテージ家具がつくられた時代のモダニズム建築は、階段も印象的なんです。ル・コルビュジエ、前川國男、坂倉準三たちが当時手がけた建築では、コンクリートや木材を使った造形的な手すりがよく用いられています。ここでも、そんな時代へのオマージュを捧げて、手すりの造形にチャレンジしました」
 手すりの素材にはナラを用いている
手すりの素材にはナラを用いている
 粘土の原寸模型での形状検討(提供:森田悠紀建築設計事務所)
粘土の原寸模型での形状検討(提供:森田悠紀建築設計事務所)
#9 ラワンの扉を引き立てる錠と
オリジナル製作の手掛け

1階トイレの引き戸はラワンで、鍵は「カワジュン」の「鎌錠 KM-17 表示錠セット」を。引き込みに支障が出ない薄さと、ミニマムなデザイン、マットな質感という理由で採用しています。
手掛けは既製の金物は取り付けずに造作でラワンの無垢材を取り付けた。
靴箱の手掛けは、見切り材と同じ半円をモチーフとした、ころんと愛らしいデザインに。ラワンの削り出しで製作しています。

#10 ノイズレスな張り方の
ガルバリウム鋼板小波板

上から下までガルバリウム鋼板小波板のラインがすっくと通る。眺めていてまったくノイズを感じさせない秘訣は、上下にジョイントをつくらないように、縦方向を約7mの長尺1枚もので仕上げているため。搬入も施工も大変でしたが、施工者の尽力によって実現しました。
左右に重なる小波板のジョイントも小口が見えづらいように重ねる向きを指示し、四隅の外壁コーナーは輪郭がくっきりと出るようにアングルを入れ、一方で入口のコーナーは輪郭を和らげるためにアングルは入れず小波板を曲げて納めています。
基礎は鋼製型枠で打ったあと、あえてモルタルで補修せずにコンクリートの質感を大切に。
アプローチの土間床のエッジの面取りも、両端まで突き通さず、必要な範囲に絞って設けることで、室内の階段ノンスリップ溝のデザインと通じる形を表していいます。



ディテールもパーツも空間も
あえて決め込めず
“その人らしさ”を大切に
 家具を設計のインスピレーションの一つにした「国分寺の家」では、見切りやコーナーのようなディテールをオリジナルでデザインすることで、家具と空間がシームレスにつながります。
家具を設計のインスピレーションの一つにした「国分寺の家」では、見切りやコーナーのようなディテールをオリジナルでデザインすることで、家具と空間がシームレスにつながります。
「もちろん家具は設計において大切な要素ですが、住まい手がとりわけ家具に愛着をもっていた、ということが、今回家具にフォーカスした理由の一つです。元を辿れば “その人らしさ” 、ということでしょうか」
家具以外のことに興味をもつ住まい手なら、また別のアプローチになっていた……と語る森田さん。
「常に設計のベースにあるのは、土地と住まい手の個性です。家具はわかりやすい一例ですが、モノだけからヒントを得ているわけではありません。土地や住まい手の雰囲気によって、おおらかに空間をまとめることもあれば、繊細につくり込むことも。周辺環境や住まい手の生活感によっては、洗練させすぎないほうがふさわしい場合もあるでしょう。住まい手の生活が建築に入った時、ちょうどよいバランスになることを考えています」
そう考えるのはどのような理由からでしょう。
「建築の設計だけを一生懸命頑張っても、住まい手の生活に合わないと、まるで似合わない服を着せているようなことになってしまいます。
また特定の作風を追求することでその作風に共感して下さる方と出会い、アップデートを繰り返してクオリティを上げていくスタンスも素晴らしいと思っていますし、その価値も理解しています。
ただ一方で、私自身は予めこのようにつくりたいという具体的なものを持ち合わせていないため、まず土地や住まい手の個性を手がかりに設計を考え始め、そこから立ち現れる、あるべき建築の姿を模索する方が自然なのです。
そして、土地や住まい手の特徴が重なるオリジナルな建築は、究極の特殊解とも言えますが、そのあるべき姿を深く考えることで、住まい手以外の人にも共感されるような普遍的な魅力を兼ね備えたものができるのではないかと考えています」
料理で言えば、究極のラーメンをひたすらアップデートしていくよりも、季節ごとに旬の食材やお客さんの雰囲気を汲み取りながらその時限りのメニューを考えるタイプ……と森田さんはおだやかに笑います。

こうしたスタンスゆえに、あえて定番のディーテルやパーツは決め込まないのが森田さんの流儀。
「機能や性能ほかさまざまな条件から何度考えても同じ方向性に収束する部分ももちろんあります。また製品によっては、消去法的な理由を積み重ねた結果として残るものも。ただいずれにせよ、こうあるべきだ、という具体的な決まりをあまりもたないようにしたいと心がけています。
ディテールやパーツだけでなく、空間に対しても同様で、リビングだから天井が高くて広くなければいけない、といった既成概念にとらわれないように努めています。住まい手のライフスタイルによっては、キッチンやお風呂が特等席ということもありますから。」

ただそれは、設計のプロセスでものすごく手間がかかるとも言えます。毎回、その土地や住まい手のキャラクターを手がかりに、ディテールやパーツをまっさらな状態から考えはじめ、検討を積み重ねて……となると、相当な労力を費やすことに。スタンダードをもつということは、そこを効率化し改善を積み重ねることができるという強みもあるのですから。
「ただ、それが自分にとっての設計の醍醐味なのです。毎回、大なり小なりチャレンジが伴うわけですが、住まい手と一緒にいまだ見ぬ建築を想像し、予定調和を超えた一度きりのものづくりの楽しみを共有しながら進めていく。そして、そうやってでき上がる建築にはある種の瑞々しさが宿る。そこに惹かれているのです」
 1階洗面所の洗面台も、同様の見切りのデザインが用いられている
1階洗面所の洗面台も、同様の見切りのデザインが用いられている
既製品とオリジナル製作に対する使い分けは、どのようにしているのでしょう?
「もちろん既製品で適したものがあれば使いますが、なければつくる、というスタンスです。機能・性能・コストのバランスを鑑み、コストパフォーマンスのバランスが適切ならオリジナルで……という考え方ですね。また住まい手がここは大事にしたいという部分や、全体の計画に影響が大きい要素であれば、少しお金をかけてでもこだわったほうがよいと思っています。そのバランス感も、プロジェクトごとに異なる気がしています」
森田さんにとってのノイズレスってなんですか?
 空間も、素材も、ディテールも、プロジェクトごとに都度考えたいという森田さん。
空間も、素材も、ディテールも、プロジェクトごとに都度考えたいという森田さん。
ただ、どの住まいにも通底する、揺るぎない基本はあります。それは、自然な雰囲気であること、美しいこと、物同士や空間同士の関係性を大切にすること、人の居場所と空気の塊を感じられるような空間づくりをすること。
そして、さまざまなものがあるべき姿で調和している状態であること。
「その調和のための力の入れ具合や抜き具合、止め方が大事だと思っています」この調和している状態、というのが、森田さんにとっての「ノイズレス」でもあります。

「“ノイズレス”と聞くと、調和していたり、自然な状態をイメージします。変に気になってしまうものがない状態、とも言えるでしょうか」 ただ何をノイズと考えるかは、ケースバイケース。
「たとえば携帯電話の着信音は、クラシック音楽のコンサートホールではノイズになりますが、ストリートライブでは車のクラクションや話し声などと入り混じってノイズと感じないように、周囲の環境や住まい手の特性によっても、何がノイズになるかは変わってきます。そこを見極めることが大切なのですね。
また過度にミニマルな方向に向かって要素を消していってしまうと、建築としては端正なものができあがっても、建築が周辺から孤立してしまったり、住まい手の生活がノイズに見えてしまったりすることもあります。住まい手の生活感、落ち着きや心地よさといったものの受け取り方は、人それぞれなので、そこを見極めて空気感や密度感をチューニングしていきたい」
音楽や映画に強い感銘を受ける時のように、感情が最大瞬間風速を迎えるような建築をつくりたい……かつて森田さんはこんなふうに考えていたそう。
「ただ今は、最大瞬間風速だけでなく、住んでいる人が自覚しないくらいの微風が吹き続けることも、大切だと思うようになって。
建築は何十年にわたって住まい手に寄り添うもの。瞬間的で鮮明な喜びをもたらすことはもちろんですが、それだけでなく、そよいでいたことにある日初めて気づくくらいの存在感で暮らしを包むことも建築だからこそ可能な本質的な価値だと思うんです。その二つを併せ持てることを、めざしています」

【プロフィール】
森田悠紀
1984年静岡県生まれ。2007年千葉大学工学部デザイン工学科建築系卒業。2007〜2008年リスボン工科大学建築学部。2009年千葉大学大学院工学研究科建築都市科学専攻修了。2009〜2012年株式会社小川広次建築設計事務所。2013〜2015年株式会社ワークヴィジョンズ。2015年森田悠紀建築設計事務所設立。2020年〜愛知産業大学非常勤講師。2022年〜千葉大学非常勤講師
森田さんのホームページ:https://yukimorita.com/
前編はこちらから→
〈このコラムで紹介したパーツ〉
・天井・枠材・建具塗装 :プラネットジャパン ウッドコート・プラネットOP
・家具用コンセント:神保電気 NK Serie KAG
・配線孔(天井):スガツネ工業 配線孔 CHC型
・カーテンレール:TOSO シエロライン
・ブラインド:タチカワブラインド シルキーカーテン
・タイル:平田タイル SES-GL
【国分寺の家】
東京都
敷地面積 100.42㎡
建築面積 44.12㎡
延床面積 79.01㎡
構造規模 木造・地上2階建て
竣工年月 2023年7月
設計 株式会社森田悠紀建築設計事務所
施工 株式会社水雅