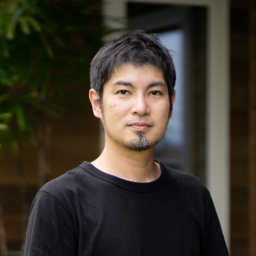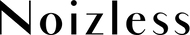無印良品の思想から生まれた、素朴で味わい深い建材たち(前編)
「作り手の気持ち」第6回目は、無印良品を運営する株式会社良品計画と、株式会社MUJI HOUSE(株式会社良品計画のグループ会社)。今回はMUJI HOUSEのリノベーション事業本部の松本さんと、良品計画の空間設計部の井澤さんにお話を伺いました。
無印良品と聞くと、雑貨や家具、アパレルや食品が思い浮かびますが、2000年代初頭より戸建て住宅の建築やマンションリノベーションを行ってきました。
戸建て住宅事業「無印良品の家」や、UR都市機構と全国の団地をリノベーションする共同事業「MUJI×UR団地リノベーションプロジェクト」、オフィスやホテル、店舗や公共施設などの建築事業を行っています。さらに、自社の空間づくりに合う建材の開発及び販売も行っています。
今回のインタビューでは、Noizlessでセレクトした「麻畳」と、「下地のまま仕上げたフローリング」「日本の木でできた直貼り遮音(L-40)フローリング」「リネンでできた壁紙」の開発の経緯について伺いました。前編・後編の2回に分けてご紹介します。

 今回取材を行った場所は、光が丘パークタウンゆりの木通り33番街(東京都板橋区)にある研修施設
今回取材を行った場所は、光が丘パークタウンゆりの木通り33番街(東京都板橋区)にある研修施設
これまでにない暮らし方を賃貸住宅で実現する、MUJI×UR団地リノベーションプロジェクト。
―今回のインタビューの前半では、「MUJI×UR団地リノベーションプロジェクト」に携わっている松本さんに、このプロジェクトから生まれた建材「麻畳」「下地のまま仕上げたフローリング」の解説をお願いできればと思います。そもそも「MUJI×UR団地リノベーションプロジェクト」とはどのような事業なのでしょうか?
〈リノベーション事業本部・松本さん〉 「MUJI×UR(ムジ・バイ・ユーアール)」は2012年にスタートしたプロジェクトです。URさんは前身の公団の時代から日本の「暮らしのスタンダード」をつくってきた組織で、MUJI HOUSEも「暮らしのスタンダード」を目指して商品開発をしてきたという点で共通点がありました。そういうところから共感が生まれ、プロジェクトがスタートしたんです。
 松本雄作さん(株式会社MUJI HOUSE リノベーション事業本部 法人リノベーション部 課長)
松本雄作さん(株式会社MUJI HOUSE リノベーション事業本部 法人リノベーション部 課長)
プロジェクトスタート当時は団地の高齢化や空き家問題が深刻化し社会問題になっていて、URさんとしては、若年層の入居促進が課題の一つになっていました。一方、MUJI HOUSEは、自分たちの理想とする暮らしを表現できる場所を探していました。そんな中、改めて団地を見てみると、広い敷地に豊かな緑、風通しや日当たりの良い住戸、もしかすると団地は、今都市に住むための場所として最も賢い選択肢かもしれないと考えたのです。
そして、URさんは全国に70万戸の住戸をお持ちの日本一の大家さんで、その数というのが私たちにとってはすごく魅力的だったんですね。それだけの数があれば、より多くの方々に暮らしのスタンダードを提供できると考えたからです。
そうして、これまでにない暮らし方を賃貸住宅で実現しようとする試みとして2012年に最初のMUJI×UR団地リノベーションプロジェクトが大阪にある「リバーサイドしろきた」という団地でスタートしました。団地のリノベーションというものが世に知れ渡るきっかけとなったプロジェクトでした。


リバーサイドしろきた(大阪)の外観とリノベーションされた住戸のモデルルーム
翌年、東京の高島平団地でMUJI×URのリノベーションを行うと、テレビや雑誌で取り上げられ、さらに注目を集めることになりました。
どちらのリノベーションも人気を博し、高島平では入居希望者の最高倍率が20倍にもなり、建設当時と同じような倍率になったと言われました。
そして3年目の2014年には全国展開をしていくことになり、これまでに関西、関東、中部、九州、北海道で、累計約70団地1,400戸以上(2025年3月時点)のリノベーションを行ってきました。今も年間100戸くらいのペースで実績が増えています。
 高島平団地(東京)のリノベーションされた住戸のモデルルーム
高島平団地(東京)のリノベーションされた住戸のモデルルーム
コンセプトは「生かす、変える、自由にできる」。
―「暮らしのスタンダードをつくる」という共通の思想を持つ2社が非常にうまく連携して実績を積み重ねているんですね。団地リノベーションを行う上で大事にしているのはどんなことですか?
〈松本さん〉 「生かす、変える、自由にできる」というコンセプトでリノベーションを行っています。「古い=悪い」ではなく、古さは団地の魅力であると捉えて生かし、コストも抑えることで横展開も可能にしています。それから、URさんと私たちで一緒に団地の暮らしに合ったパーツ開発をしているのも特徴ですね。
例えば、何十年も経って飴色になった和室の敷居や鴨居は、ヴィンテージジーンズのように味があっていいものと捉えて生かすようにしていますが、古いお風呂やキッチンなどの水回りの設備は、現代の暮らしに合うように積極的に変えるようにしています。
ただ、そこに一般的なメーカー品のキッチンをポンと置くと違和感が出てしまう。であれば、MUJI×URのコンセプトに合ったキッチンをつくってしまおうということで、開発を行いました。
「麻畳」や「下地のまま仕上げたフローリング」もそのようにして生まれた建材なんです。
家具を置いても傷みにくい麻で畳をつくる。

―MUJI×URの世界観に合わせて建材の開発までしているのがすごいですね。では「麻畳」について詳しく教えて頂けますか?
〈松本さん〉 「麻畳」は団地の魅力を生かす最も優れた商品の一つです。そもそも古い団地で3DKの部屋だったりすると、3部屋とも和室なんですよ。和室も若い方に敬遠されがちなんですが、和室を全部洋室化すると非常にコストが掛かってしまいます。というのも、URさんの団地では、畳だった部屋を洋室化する時に、畳と同じ遮音性を求められるからなんですね。
だったら「洋室として使える畳」を開発すればいいのではという考えに至り、そうしてできたのが「麻畳」です。開発までには様々な素材が試されたのですが、最終的に「麻生地」を巻くことで商品化ができました。
麻はイ草よりも強いので、ベッドやダイニングテーブルを置いても傷みにくいですし、元々こういう色なので日焼けによる色褪せもほとんどしないんです。
床座でも椅子座でもどちらでも自由に選べるというのも、MUJI×URのコンセプトでもある「自由にできる」部分として機能しています。


で全国的に畳の需要が減っている中、一度洋室化された部屋は二度と和室に戻ることはありません。「麻畳」を使うことは畳屋さんを守ることにもつながっています。
同じように見える部屋でも寸法が微妙に異なるため、畳をきれいに敷き込むには畳屋さんが採寸して製造する必要があるからですね。畳表の麻生地は良品計画が提供しており、それを畳にして施工するのは全国の畳屋さんの仕事になるんです。
MUJI×UR用に開発した建材ですが、今では団地以外の戸建てや、マンションリノベーションでも使って頂いています。店舗では無印良品 グランフロント大阪で扱っていますので、一般の方がご自宅用に使いたい場合はそこで注文することもできます。
経年変化した空間に調和する、下地のままのフローリング。
―コストと機能を両立した麻畳。シンプルですが、とても画期的ですね。次に「下地のまま仕上げたフローリング」について教えて頂けますか?
〈松本さん〉 これは無印良品の思想の「素材を生かす」という考え方から生まれたフローリングです。
元々1×6(303mm×1,818mm)サイズの合板フローリングというのは、303mm幅の中にフェイクの溝を2本や4本入れていて、フローリングがたくさん張られているように見せているんです。そうではなく、基材そのものを生かしたフローリングを作れないか?と考えて開発をしました。
基材のラワン合板そのものにクリア塗装をしているんですが、そもそも合板は仕上げ用ではないので、同じ色や木目のものがないんですね。赤っぽいものや白っぽいもの、黄色っぽいものなど色々なものがあります。そこで、工場の方で赤っぽいものだけを選んでもらうよう手間をかけて選別しています。
ただ、赤っぽいものの中でもけっこう色幅があるんですけど、それに関してはそのまま使っています。多少の色のばらつきがあっても、同じラワン合板であることには変わりませんので。

開発で困ったことは、URさんで採用するにあたり、耐荷重や耐摩耗性などの基準をクリアする必要があるのですが、合板にクリア塗装をして仕上げた建材のJIS規格の規定がないことでした。そこで、同等の性能を満たしていることを証明するべく様々な試験を行い、すべてクリアすることで採用になりました。そこの過程はとても苦労したところです。
MUJI×URでは古い敷居鴨居をそのまま残すようにしていますが、それに合うフローリングがなかなかないというのも開発の理由です。人によって好みは分かれますが、ラワン合板くらいラフだと飴色になった敷居鴨居ともよく合うなあと思います。ただ、床を張る職人さんからは「これで終わりでいいの?これから仕上げ材を貼るんだよね?」と聞かれることがあります(笑)。

妄想から始まる新たな建材開発。
―まさに無印良品さんの思想を体現した建材ですね。最後に、今後の建材開発における展望をお聞かせ頂けますか?
〈松本さん〉 MUJI×URのはじめの頃は「必要な建材がないからつくる」という想いで開発を行っていましたが、今は必要なものは一通りそろっています。そんな中で、これからは団地で廃棄される端材を使った地産地消な製品など、よりサステナブルなものを目指して開発をしていこうとしています。

あと、5年くらい前から僕は「団地から考える暮らしの知恵100」という妄想的なコラムを書いていて、そこから生まれてきた商品もありますし、今後もそこから商品化されるものがあるかもしれません。
 団地から考える暮らしの知恵100
団地から考える暮らしの知恵100
– 前編はここまでです。次回の後編では、空間設計部の井澤さんに「日本の木でできた直貼りフローリング」「リネンでできた壁紙」について詳しく解説をして頂きます。