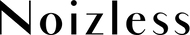ベントキャップの話
聞き馴染みのないパーツ
「ベントキャップ」という部材をご存知でしょうか。ほとんどの方は聞き馴染みの無い部材だと思います。
ベントキャップとは吸気口・排気口の外壁側の開口部に設置する蓋で、室内に雨水や虫を侵入させない役割を持つ部材です。
一戸あたり8個前後が設置され、機能面では必要不可欠な部材です。しかし、外観のデザイン性を考える上では意匠性を損なう部材となり、特にファサード(建物の正面から見た外観)にベントキャップが並ぶことでノイズが生まれ、時に垢抜けない印象を与えてしまいます。
私はこれまで述べ1000組以上の注文住宅のご相談を受け、様々な意匠性に関するご要望を伺いましたが「ベントキャップをファサードから見えないようにしたい!ベントキャップはこの商品にして欲しい!」といったご要望は聞いたことがありません。
外観をデザインする上で外壁の素材や色、窓の形状等に気を使う方は多いですが、ベントキャップの位置やデザインにまでこだわりを持った方は少ないのが現状です。
 場所によって数種類のベントキャップを使い分けている 設計:株式会社おうちLABO
場所によって数種類のベントキャップを使い分けている 設計:株式会社おうちLABO
小さな当たり前を変化させる
そもそも、なぜベントキャップを設置する必要があるのでしょうか。
それは、2003年に改正建築基準法が施行され「シックハウス対策」が義務化になった影響です。これにより換気設備の設置が義務化され、居室や天井裏への換気が必要になったことで、いわゆる「24時間換気システム」が普及し、吸気口や排気口の設置個数が増え、ベントキャップの数も必然と増えていったという背景があります。
ではノイズが生まれないデザインにするにはどうしたら良いか。それは「小さな当たり前を変化させる」ことです。住宅にはベントキャップを筆頭に巾木(はばき)・窓枠・建具枠・把手(とって)・雨樋・水切・物干といった決して家の主役とは言えない当たり前に使われるパーツが多くあります。この「小さな当たり前」のデザインを変化させることで既視感のある住宅から脱却し、シンプルかつどこか丁寧さを感じる洗練されたデザインを実現することができます。
 外壁に色を合わせることで目立たなくしている 設計:株式会社レクト
外壁に色を合わせることで目立たなくしている 設計:株式会社レクト
神は細部に宿る
近代建築の巨匠ミース・ファン・デル・ローエは、「神は細部(ディテール)に宿る」という名言を残しています。建築家の想いは建物のディテールに表れ、細部の造り込みや納まりの綺麗さが建築全体の値打ちを決めるという意味です。
「小さな当たり前」を変化させ細部までこだわったというプロセスこそが「愛着が湧く住まい」になる秘訣で、豊かな暮らしに繋がるのかもしれません。
*この記事はNoizless誌 Vol2からの転載しております。

二級建築士・宅地建物取引士・二級FP技能士
1989年生まれ。埼玉県戸田市出身。株式会社おうちLABOにて「建築家とつくる家づくり」をコンセプトに住宅営業がいない住宅会社を経営。自身も建築士として様々なコンテストを受賞しており、デザインと住み心地を追求した住まいを埼玉・東京を中心に展開。建築士が土地仲介からFPまで行う独自のスタイルで延べ1000組以上の顧客の問題解決を行い、住まいのコンシェルジュとしてワンストップサービスを展開中。
株式会社おうちLABO