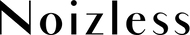見付けの話
「どうすればデザイン性の⾼い住宅になりますか?」
これは、間取りや仕様のお打ち合わせをしている中で、デザイン思考の⾼いお施主様からよくい ただくご質問のひとつです。
前提としてデザインというのは住⼈⼗⾊で正解はないと考えています。
ただその中でも、ある部分に意識を向けるだけで、シンプルだけど洗練された印象にできるポイントがあります。 それが「⾒付けの厚み」です。
⾒付けの重要性
 建具枠の⾒付け
建具枠の⾒付け
 窓枠の⾒付け
窓枠の⾒付け
「⾒付け」とは、建具枠や窓枠等の枠材や⼱⽊、カウンター、⾒切り材などの部材を正⾯から⾒たときの厚みの名称です。
私もこれまでに1000組以上のお施主様と打ち合わせをしてきましたが、お施主様から「⾒付け」 というワードを聞いたことはほとんどなく、ご存じない⽅が⼤半だと思います。
しかし、⾒付けを「厚く⾒せるか」「薄く⾒せるか」によって、空間の印象は⼤きく変わり、⼨法でいえば数センチにも満たないディテールですが、この数センチで住宅のデザイン性は⼤きく変わるといっても過⾔ではないでしょう。
線を減らし空間を整える
 ⾒付けの薄い笠⽊材
⾒付けの薄い笠⽊材
 見付けの薄い窓枠(fit frame)
見付けの薄い窓枠(fit frame)
 存在感のない床⾒切り材
存在感のない床⾒切り材
⼈間の⽬は、空間を「⾯」と「線」の情報で捉えています。
線が多くなるほど視覚的なノイズが増え、空間は雑然とした印象になります。そこで有効なのが⾒付けを薄くするという設計⼿法です。
⾒付けを極限まで細くしたり、周囲と同化させるように設計することで線の情報量が減り、空間が整理されて⾒えるのです。これが、⾒付けを薄くすると「シンプルに⾒える」と⾔われる理由の⼀つです。
また、⾒付けが厚くなると、枠の段差や出っ張りによって影が落ちやすくなります。 影は空間に奥⾏きを与える⼀⽅で、視覚的なコントラストを増やす原因にもなります。
薄い⾒付けは、その影を最⼩限に抑え、壁⾯全体を⼀枚の「静かな⾯」として整える効果があります。また余⽩を活かしたり、ノイズを減らして主役を際⽴たせるという役割を果たしているともいえるでしょう。
⾒付けを「薄く」するディテール
 線を減らしたシンプルな空間
線を減らしたシンプルな空間
近年では、「⾒付けを薄く⾒せる」ことがデザイン性の⾼い住宅会社のトレンドになっています。これは、視覚的なノイズを減らし、より洗練されたミニマルな空間を実現するための⼯夫です。
例えば、カウンターの天板や笠⽊、建具枠や窓枠などが分厚く⾒えると、それだけで「重さ」や「野暮ったさ」を感じさせてしまいます。反対に、厚みを最⼩限に抑えることで、線がシャープになり、空間がすっきりと広く感じられるのです。
この薄さを成⽴させるためには、構造的な⼯夫や下地の精度、場合によっては特注部材の採⽤など、⾼度な設計・施⼯技術が求められます。
また、⾒付けの薄さは建設会社や設計者がどれだけ空間に気を配っているかのバロメーターとも⾔われています。このようなディテールは建設会社・設計者・職⼈の連携によって初めて成り⽴つチームプレイの賜物とも⾔えるでしょう。
デザインは⾜し算ではなく引き算

タイルと調和した⾒切り材
とはいえ、⾒付けを薄くすることが常に最善とは限りません。
強度や施⼯性、将来的なメンテナンス性も考慮しながら要所要所で部材を選定する必要があります。
たとえば⼱⽊を極端に薄くすると、掃除機などで壁を傷つけるリスクが増えたり、建具枠の⾒付けをゼロに近づければ、⾒た⽬の美しさとは裏腹に下地処理やクロス納まりの難易度が⼀気に跳ね上がり、施⼯技術が求められる納まりになるため、施⼯できる建設会社は限られてきます。
だからこそ重要なのは、ただ薄くするのではなく「どこを薄く⾒せるか」「どこに厚みを残すか」の⾒極めです。
「何を加えるか」ではなく「何を削るか」がデザインする上で⼤切な思想だと私は考えています。
ディテールに宿る「住まいの豊かさ」
 線を減らしたシンプルな空間
線を減らしたシンプルな空間
住宅は、家族が⻑い時間を過ごす⽣活の場であり、空間の⼼地よさや美しさは⽇々の暮らしの質に直結します。そしてその⼼地よさは、たった1cmにも満たない「⾒付け」の扱いひとつで⽣まれたり、損なわれたりするのです。
⼩さな厚みの選択が、住まいの豊かさを⼤きく変える。だからこそ、その「1cm」にこだわってみるのはいかがでしょうか。

二級建築士・宅地建物取引士・二級FP技能士
1989年生まれ。埼玉県戸田市出身。株式会社おうちLABOにて「建築家とつくる家づくり」をコンセプトに住宅営業がいない住宅会社を経営。自身も建築士として様々なコンテストを受賞しており、デザインと住み心地を追求した住まいを埼玉・東京を中心に展開。建築士が土地仲介からFPまで行う独自のスタイルで延べ1000組以上の顧客の問題解決を行い、住まいのコンシェルジュとしてワンストップサービスを展開中。
株式会社おうちLABO