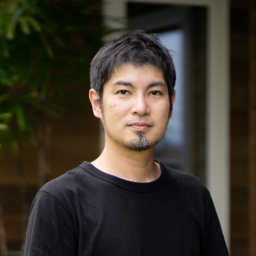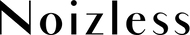無印良品の思想から生まれた、素朴で味わい深い建材たち(後編)
株式会社MUJI HOUSEの松本さんと、株式会社良品計画の井澤さんへのインタビュー。後編では井澤さんに「日本の木でできた直貼り遮音(L-40)フローリング」「リネンでできた壁紙」について伺います。
法人向けに空間をトータルで提案する空間設計部。
――井澤さんは良品計画の中の空間設計部で商品開発を担当されているということですが、そもそも空間設計部とはどんなことをしている部署なのですか?
〈井澤さん〉 空間設計部はオフィスや宿泊施設、公共施設などB(法人)向けの空間事業と法人向け空間商材の開発をメインにしている部署になります。一方、松本さんが所属している株式会社MUJI HOUSEは、木造住宅や集合住宅のリノベーションなど、C(一般消費者)向けをメインにしているという違いがあります。

井澤充さん(株式会社良品計画 空間設計部 空間事業課 東京事務所 商品開発担当MD)
空間設計部では空間をつくることと、そこで使う什器や建材をつくることを並行してやっています。例えばオフィスに納めるロッカーやテーブルなども開発していますし、床材や壁材などの開発も行っています。

左)スチールロッカー 両開き ロー、(右)スチールロッカー 個人ロッカー 6人用
永く使えて、資源が循環するものづくり。
―空間だけをつくるのではなく、そこで使われる什器や建材を含めた提案ができるんですね。ちなみに建材などの商品開発をする上で大事にしているコンセプトはどんなことですか?
〈井澤さん〉 商品開発を行う上で、資源の循環や永く使えることを重視しています。その考え方を分かりやすくしたものがこちらの絵になります。

良品計画 空間設計部 コンセプト図
森林資源の循環、鉄や紙などを再資源化する循環、カスタムやリペアなどをしてものを永く大事に使うことが表現されています。
そして、そのようなものづくりの考え方を「私たちのものづくり8つの手法」として身近なものに例えながら掲げています。
例えば、「形が悪い野菜でも味は美味しいから廃棄せずに食べたいよね」と私たちは考えていて、それが木材であれば、節があっても普通に使えるなら積極的に採用しています。それが一つ目の「見た目だけで判断しない」という考え方ですね。
 良品計画 空間設計部 コンセプトページ
良品計画 空間設計部 コンセプトページ
他にも、「再資源化にこだわる」、「地域資源を使う」、「あるものを活用する」、「簡素を追求する」、「丈夫につくる」、「規格を活かす」、「分解できるようにする」といったことを掲げています。
林業の活性化のために国産材の利活用を考える。
――無印良品さんの思想に基づいて、新たに法人向けの什器・建材の開発が始まったところなんですね。ところで、森林資源の循環を進めるために、国産材の利活用にも力を入れていると伺いました。
 〈井澤さん〉 日本は国土の66%が森林で、世界的に見ても森林大国と言えるほどの森林面積があります。ただ、立木の価格が安いために、林業は補助金に頼らないと成り立ちにくいというのが現状です。そうすると山を管理する人や、木を伐る人、新しく植える人がいなくなります。
〈井澤さん〉 日本は国土の66%が森林で、世界的に見ても森林大国と言えるほどの森林面積があります。ただ、立木の価格が安いために、林業は補助金に頼らないと成り立ちにくいというのが現状です。そうすると山を管理する人や、木を伐る人、新しく植える人がいなくなります。
そうして山が手入れされなくなると、水害などの災害も起こりやすくなります。災害が起これば復旧に税金が使われることになりますし、山間部に住む人もいなくなるので、さらに山が遠いものになっていきます。
やがて森林資源が枯渇していくと、森林が持つ炭素を固定する役割も失われ、地球温暖化が促進されます。
山だけの問題ではなく、都市部に住む人にも影響を及ぼす“負のスパイラル”ができ上がってしまっているのが現状なんですね。この課題に対し空間設計部としては、木材を無駄なく、多く活用することで立木の価格を上げていくことと、木材活用の啓蒙が大事だと思っています。
まず木をたくさん使うと価格が安定していくと考えられます。そうすると、林業が再び産業化して地域の活性化につながります。そして、新しい木が植えられるようになり適切に山が管理され、いい循環が生まれるのではないかと考えているからです。
 山のダイゴミ展の様子
山のダイゴミ展の様子
ただ、木をたくさん使うのが簡単ではないため、まずは無駄なく使うことと、木を使うことの啓蒙から取り組むことにして、無印良品 銀座内のATELIER MUJI GINZAで「山のダイゴミ展」という”木を余すことなく使う”ものづくりの可能性を探る企画展を開催しました。
節のある国産ナラ材を使った突板フローリング。
―啓蒙活動として企画展も開催しているんですね。これからご紹介を頂く「日本の木でできた直貼りフローリング」も、そういった課題解決を目指してつくられた建材なのでしょうか?
〈井澤さん〉はい、ここにある「日本の木でできた直貼りフローリング」と「日本の木でできた突板フローリング」「日本の木でできた直張り遮音(L-40)フローリング」の3つが同じシリーズになっていまして、表面に国産のナラの突板を使っています。「日本の木でできた突板フローリング」は基材にも国産材(針葉樹合板)を使っています。


ナラの突板は、通常節があるものははじかれてしまうのですが、そのような材料を積極的に使うようにしています。建材は安全であることは大事ですが、見た目に関しては、過去のクレームによってどんどん売り手側の基準が上がり、過剰になっているケースがあります。不特定多数の方に向けて売る時に、クレームが起こらないように基準を上げていくからだと思うんですね。
そうではなく、「節がある見た目が気にならない」という方に使って頂けたらと考えて、この商品をつくりました。過剰品質を求めないことで、未利用材を減らし、木を無駄なく使うことができます。
ちなみにこの突板の表面の塗装はかなり強いものにしており、高い耐摩耗性と対傷性を持っています。それは我々がオフィスなどの法人向けの建材を扱っているからなんですね。最近は働く場と住む場の境界が曖昧になっていて、オフィス内もくつろげる空間が求められるようになっています。ですので、住宅に限らず、土足で使うようなオフィスやホテルなどの空間にも使って頂いています。
最終的に土に還る、植物だけでできた壁紙。
―冒頭で話された「見た目だけで判断しない」という考え方が体現された床材なんですね。次にいったん国産材の話から離れまして、「リネンでできた壁紙」について解説をお願いできますか?
〈井澤さん〉日本の壁紙は塩ビでできたビニルクロスが主流で、全体の9割くらいを占めているんじゃないかなと思います。循環という観点で考えた時に、壁に塩ビのものを張って、最終的にそれを回収して資源として循環していけるかというと、それは難しい。
そこで、僕らが壁紙を提供する場合、どういうものがいいかと考えました。一つは循環が考えられたものにしたいということ。そして、壁紙というよりも「素材を壁に張る」みたいなイメージのものがいいのではないかという話になりました。
そうしてつくったのが「リネンでできた壁紙」です。ビニルクロスはバインダー(接着剤)で固められていますが、これは水流の針で繊維を絡ませるスパンレースという製法が使われていて、麻の繊維と植物由来の繊維だけでつくられているんです。


触り心地がやわらかくて、張った状態もふわっとしていて壁っぽくないんですよね。着色をしていないので生成りの色になっています。植物だけでできているので、埋めればやがて土に還ります。
あとは幅が600mmと小さめなのも特徴ですね。一般的な壁紙の幅が1mくらいなので、それよりも小さく張りやすい寸法になっています。
こちらは昨年の9月に発売したばかりの商品なので、これからお客様の感想を集められたらと思っています。

エンドユーザーも巻き込んだ商品開発のサイクルを期待。
―自然素材ならではの優しい表情が魅力的な壁紙ですが、最終的に処分する時のことまで考えられているんですね。最後に、今後の建材づくりの展望をお聞かせ頂けますか?
〈井澤さん〉空間設計部には、ものづくりをしている部門と建築や空間をデザインする部門がありますので、空間とマッチした建材を見せることができます。それに無印良品の店舗も、空間や建材を表現できる場所になっています。
法人向けの商品として開発した商品もエンドユーザーが見られる場所に使われているので、エンドユーザーからの支持を受けて次の商品開発につながるというサイクルが生まれるといいなと思っています。
それから、今たくさんのアイデアやテーマでいろいろな内装材や什器をつくっていこうとしていて、まだ開発に至っていないタネみたいなものがたくさんあります。少し絞り込む必要があるくらいなのですが、循環ができて永く使える商品を今後も開発していきたいと思います。

前編・後編の2回に渡ってご紹介させて頂いた株式会社MUJI HOUSEの松本さんと、株式会社良品計画の井澤さんへのインタビュー記事は以上となります。
MUJI×URという団地リノベーションプロジェクトの中で生まれた建材や、永く使えて資源が循環することをコンセプトに据えた、無印良品らしい建材の数々。
建材について考える時、デザイン性や機能性、価格などに注目しがちですが、それとは異なる価値がそれぞれの建材に込められているのが分かりました。
麻でできた畳や、節が見られる突板のフローリング。その背景には社会的な課題解決に取り組む開発者たちの姿があります。
建材を選ぶ時にどんなことを判断基準にするべきか。改めてそんなところに立ち返り、家づくりについて考えてみてはいかがでしょうか?